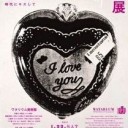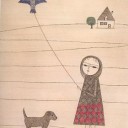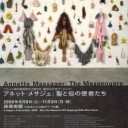「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展
2011年3月10日 芸術
新聞の絵画解説面で紹介されていたのを読んだエネが、
「わたし、この絵、好き!こういう絵が、好きなの!」
と言ったので、学校帰りのエネと待ち合わせて、水天宮のミュゼ浜口陽三ヤマサコレクションへ。
二人であーだこーだ言いながらひとまわりして、ふたまわり目は自由行動。
お土産物屋さんで画集と絵葉書を買い、美術館のカフェでお茶&ケーキ。
エネの制服姿を見ることができるのも、あと2年なのだなあと思うとちょっとしんみり。
地下鉄に乗る前に、水天宮でお参りした(←安産の神様)。
「わたし、この絵、好き!こういう絵が、好きなの!」
と言ったので、学校帰りのエネと待ち合わせて、水天宮のミュゼ浜口陽三ヤマサコレクションへ。
二人であーだこーだ言いながらひとまわりして、ふたまわり目は自由行動。
お土産物屋さんで画集と絵葉書を買い、美術館のカフェでお茶&ケーキ。
エネの制服姿を見ることができるのも、あと2年なのだなあと思うとちょっとしんみり。
地下鉄に乗る前に、水天宮でお参りした(←安産の神様)。
NO MAN’S LAND @旧仏大使館
2010年2月15日 芸術
フランス大使館旧庁舎で行われているアート・プロジェクトで、友人の音楽家がライヴを演るってんで、友人Saと出かけた。
ライヴも、パフォーマンスも、展示も、くつろいだ感じで、楽しめた。
大使の部屋には金庫があって、Saが強盗しているような写真を撮って笑った。
夜は、音楽家や芸術家たちと食事&飲みへ。
すっごい量のビール&日本酒を深夜まで飲んだが、気持ちよく飲んだせいか、今朝はすっきり。太極拳の稽古にもちゃんと出かけられたよ。
ライヴも、パフォーマンスも、展示も、くつろいだ感じで、楽しめた。
大使の部屋には金庫があって、Saが強盗しているような写真を撮って笑った。
夜は、音楽家や芸術家たちと食事&飲みへ。
すっごい量のビール&日本酒を深夜まで飲んだが、気持ちよく飲んだせいか、今朝はすっきり。太極拳の稽古にもちゃんと出かけられたよ。
江戸好きのカデットがずっと行きたがっていた博物館へ。
駅へ向かう道すがら、
「カデットちゃんみたいな可愛い女の子とお出かけできるなんて、お母さん、嬉しい!」
と言ったら、ちょびっとひかれた…
(言いながら自分でも、オッサンみたいだと思ったんだけどね。)
眺めの良い7階のレストランにて天ざるで腹ごしらえ。
6階の日本橋を渡り、6~5階の展示を回った。
6割強が江戸ゾーンで、残りが東京ゾーン(明治・大正・昭和)という感じ。
「江戸のくらしがわかる絵事典」を愛読しているカデットは、江戸に詳しい!
あらゆる展示物を、スミからスミまで見て、私にいろいろと説明してくれて、
まるで専用のガイドさん。徳川家の系図にもなかなか通じている。
「綱吉って、絵が上手だねえ」
と、掛け軸に見入ったりして。
お姫様が乗るかごに実際に入ったときは、感激のあまり(?)相当鼻息荒かった!
しかし、東京ゾーンになると、興味のレベルが下がる。
「明治になると、西洋の真似ばかりして、日本の良さがなくなっていくようで、イヤ」
なんだそうで、しまいには、
「ずっと鎖国してればよかったのに」
と言い出した。
鎖国してたら、お母さんとパパは出会わなくて、カデットも生まれてこなかったんだけどね…
とはいえ、人力車やダルマ自転車に乗ったり、電話ボックス第一号に入って話をしたり、昔の家に上がったり、いろいろ体験して、写真も撮りまくって、それなりに楽しんだ。
鹿鳴館やニコライ堂や銀座の街並みの仕掛けもなかなか良くできていたし。
最後に、1階の和風カフェで「サツマイモぜんざい」と抹茶ラテを堪能。カデットの大好物、和三盆をお土産に。
ミュージアムショップでは、ガイドブックと万華鏡を購入。
その後、お隣の国技館の前をウロウロしていたら、数人のお相撲さんに遭遇。
隅田川を少しお散歩した。
楽しいお出かけだった。
帰りの大江戸線の中でわたしは眠ってしまったけれど、
「次、青山一丁目だよ」と、そっとカデットが起こしてくれた。
駅へ向かう道すがら、
「カデットちゃんみたいな可愛い女の子とお出かけできるなんて、お母さん、嬉しい!」
と言ったら、ちょびっとひかれた…
(言いながら自分でも、オッサンみたいだと思ったんだけどね。)
眺めの良い7階のレストランにて天ざるで腹ごしらえ。
6階の日本橋を渡り、6~5階の展示を回った。
6割強が江戸ゾーンで、残りが東京ゾーン(明治・大正・昭和)という感じ。
「江戸のくらしがわかる絵事典」を愛読しているカデットは、江戸に詳しい!
あらゆる展示物を、スミからスミまで見て、私にいろいろと説明してくれて、
まるで専用のガイドさん。徳川家の系図にもなかなか通じている。
「綱吉って、絵が上手だねえ」
と、掛け軸に見入ったりして。
お姫様が乗るかごに実際に入ったときは、感激のあまり(?)相当鼻息荒かった!
しかし、東京ゾーンになると、興味のレベルが下がる。
「明治になると、西洋の真似ばかりして、日本の良さがなくなっていくようで、イヤ」
なんだそうで、しまいには、
「ずっと鎖国してればよかったのに」
と言い出した。
鎖国してたら、お母さんとパパは出会わなくて、カデットも生まれてこなかったんだけどね…
とはいえ、人力車やダルマ自転車に乗ったり、電話ボックス第一号に入って話をしたり、昔の家に上がったり、いろいろ体験して、写真も撮りまくって、それなりに楽しんだ。
鹿鳴館やニコライ堂や銀座の街並みの仕掛けもなかなか良くできていたし。
最後に、1階の和風カフェで「サツマイモぜんざい」と抹茶ラテを堪能。カデットの大好物、和三盆をお土産に。
ミュージアムショップでは、ガイドブックと万華鏡を購入。
その後、お隣の国技館の前をウロウロしていたら、数人のお相撲さんに遭遇。
隅田川を少しお散歩した。
楽しいお出かけだった。
帰りの大江戸線の中でわたしは眠ってしまったけれど、
「次、青山一丁目だよ」と、そっとカデットが起こしてくれた。
次女の誕生日・阿修羅展
2009年5月23日 芸術 コメント (5)
今日は次女の誕生日! 9歳なり~!
「おたんじょうびおめでと! お母さんの可愛いちゃん!」
しかし、次女は浮かない顔…
「わたし、大きくなりたくないの…」
「なんで?」
「だって、大きくなったら、お母さんに甘えられなくなるでしょ?」
「次女ちゃんが、どんなに大きくなっても、お母さんに甘えてもいいよ」
「ほんと?じゃあ、お外では9歳で、おうちの中では1歳の赤ちゃんになる!」
おいおい…・
でもって、本日はお誕生日イベント第一弾。
次女が今一番、行きたいところへ行く!そこは、上野の博物館でやっている阿修羅展!
夫と私と次女で(長女は部活)!
昨日の新聞で読んだ、「炎天下で2時間の列」というのを避けるべく、4時前に家を出た。
そしたら5時前について、待ち時間は30分ですんだ。
予習ばっちりの次女がしてくれる、八部衆像や十大弟子像の解説を聞きながらまわった。
すごくためになったよ!
彼女は迦楼羅(かるら)がお気に入りで、360度眺めた後、彼が向ける視線の先に張り付いて、見詰め合っていた。
「なんだか、ドキドキする…」
だって…。
私が、
「なんだかみんな、困ったよーな顔してるね」
と言ったら、
「困ってるんじゃないの! 耳を澄ましてるの!」
すみません…
沙羯羅(さから)はあどけない表情で、緊那羅(きんなら)の三つ目と一角は異形ながらも端正で、五部浄(ごぶじょう)はイケメンだ…
って、まるで、ボーイズ・ウォッチング?
メインの阿修羅は、まず、見物人の多さに圧倒された。それだけでオーラがあるような錯覚を感じる。
次女は、スロープの、中ほどの、正面になる位置から、じっくりと眺め、そして、
「もういい」
と言って、降りていった。
「ほんとにもういいの?」
「うん、だって、他にも見たい人がたくさんいるからね」
像の周りは大人が何重にも取り巻いていて、彼女の目線ではほとんど見えない。ので、ぐるりと一周して、会場を出た。
おみやげ物やさんで、目録と絵葉書を数枚買った(もちろん、迦楼羅のも!)
地下鉄に乗って帰途につき、駅で長女と待ち合わせ、246沿いのステーキハウスで食事をした(正直、美味しくなかった…せっかくの誕生日なのに…二度と行かないぜ!)。
ところで、次女の「今日のおしゃれコーデ」とやらは、ベージュのカットワーク刺繍のブラウスに、深緑のタータンチェックのガーゼ素材のスカート。フランスのお土産のカバンをもって、洗面所でプチ・ゲランのコロンをシュッ! 髪にはカチューシャ、爪には、小さなデコシールを張って、もー、いっぱしのおしゃれさん。
来年は、ティーンエイジャーか…。
あたしが年をとるはずだ…。
「おたんじょうびおめでと! お母さんの可愛いちゃん!」
しかし、次女は浮かない顔…
「わたし、大きくなりたくないの…」
「なんで?」
「だって、大きくなったら、お母さんに甘えられなくなるでしょ?」
「次女ちゃんが、どんなに大きくなっても、お母さんに甘えてもいいよ」
「ほんと?じゃあ、お外では9歳で、おうちの中では1歳の赤ちゃんになる!」
おいおい…・
でもって、本日はお誕生日イベント第一弾。
次女が今一番、行きたいところへ行く!そこは、上野の博物館でやっている阿修羅展!
夫と私と次女で(長女は部活)!
昨日の新聞で読んだ、「炎天下で2時間の列」というのを避けるべく、4時前に家を出た。
そしたら5時前について、待ち時間は30分ですんだ。
予習ばっちりの次女がしてくれる、八部衆像や十大弟子像の解説を聞きながらまわった。
すごくためになったよ!
彼女は迦楼羅(かるら)がお気に入りで、360度眺めた後、彼が向ける視線の先に張り付いて、見詰め合っていた。
「なんだか、ドキドキする…」
だって…。
私が、
「なんだかみんな、困ったよーな顔してるね」
と言ったら、
「困ってるんじゃないの! 耳を澄ましてるの!」
すみません…
沙羯羅(さから)はあどけない表情で、緊那羅(きんなら)の三つ目と一角は異形ながらも端正で、五部浄(ごぶじょう)はイケメンだ…
って、まるで、ボーイズ・ウォッチング?
メインの阿修羅は、まず、見物人の多さに圧倒された。それだけでオーラがあるような錯覚を感じる。
次女は、スロープの、中ほどの、正面になる位置から、じっくりと眺め、そして、
「もういい」
と言って、降りていった。
「ほんとにもういいの?」
「うん、だって、他にも見たい人がたくさんいるからね」
像の周りは大人が何重にも取り巻いていて、彼女の目線ではほとんど見えない。ので、ぐるりと一周して、会場を出た。
おみやげ物やさんで、目録と絵葉書を数枚買った(もちろん、迦楼羅のも!)
地下鉄に乗って帰途につき、駅で長女と待ち合わせ、246沿いのステーキハウスで食事をした(正直、美味しくなかった…せっかくの誕生日なのに…二度と行かないぜ!)。
ところで、次女の「今日のおしゃれコーデ」とやらは、ベージュのカットワーク刺繍のブラウスに、深緑のタータンチェックのガーゼ素材のスカート。フランスのお土産のカバンをもって、洗面所でプチ・ゲランのコロンをシュッ! 髪にはカチューシャ、爪には、小さなデコシールを張って、もー、いっぱしのおしゃれさん。
来年は、ティーンエイジャーか…。
あたしが年をとるはずだ…。
進める荒井良二のいろいろ展
2009年3月27日 芸術 コメント (2)
を、世田谷文学館へ見に行った、昨日、次女と長女と、3人で。
「荒井良二さんの展覧会に行くには、世田谷線に乗っていくのがふさわしい!」
と、娘たちが言うので、わざわざ遠回りして、ちいさなちいさな、ゆっくりゆっくりの電車に乗って。
展覧会場で、わたしたちは3人とも夢中になって、隅から隅まで眺めつくして楽しんだ。
荒井良二って、すごい進化していて、最近は特に進化のスピードが速まっていると感じた。
最新作の「えほんのこども」は、もはや、絵本というカテゴリーを飛び出している!
現代美術の最先端だ!
スェーデンで行われたアストリッド・リンドグレーン賞の授賞式で、彼は「ありがとう、アストリッド」という歌を作って、ギターを弾きながらスェーデン語で歌った。
スェーデン人たちは泣いていた。
素晴らしいね!
おみやげ物屋さんで、展覧会の目録と、「えほんのこども」と、絵葉書を5枚買った。
お昼は、サンマルクというベーカリーレストランで食べた。ここが、すごい優秀なの!
スープ、前菜2種、メイン、デザート、飲み物に加えて、なんとパンが食べ放題!
焼きたてのパンを籠に盛ったお姉さんが、しょっちゅうテーブルを回ってきて、好きなだけパンを取らせてくれる。しかも! 一回につき4~5種類のパンがあって、回ってくるたびにパンの種類が違う! ブルーベリーパン、かぼちゃパン、黒ごまチーズパン、野菜パン、ミルクパン、バジルパン、よもぎパン、チョコレートパンetc…
欲張りな私たちは、お腹が破裂しそうなくらいに食べてしまった。
それで、会計は3人で6千円弱!
いっぱい食べた次女のお腹が、膨らんでいた…(わたしもだけど!)
娘たちはふたりとも、ちっさい頃は、ご飯の後はいつも、おなかがぽこっと膨らんでいて、天使みたいだなぁと思っていた。
私は、ふたりの天使と暮らすことができたんだね。幸せな母だね。
そして。
世田谷線で、座っている次女の前に年配のご婦人が立ったとき、次女がそっと立って、席を譲ろうとした。ご婦人は、
「もうすぐ降りるからいいのよ」
と、辞退したのだが、そのとき私は、次女を生んで、ほんとによかったと思った。
「荒井良二さんの展覧会に行くには、世田谷線に乗っていくのがふさわしい!」
と、娘たちが言うので、わざわざ遠回りして、ちいさなちいさな、ゆっくりゆっくりの電車に乗って。
展覧会場で、わたしたちは3人とも夢中になって、隅から隅まで眺めつくして楽しんだ。
荒井良二って、すごい進化していて、最近は特に進化のスピードが速まっていると感じた。
最新作の「えほんのこども」は、もはや、絵本というカテゴリーを飛び出している!
現代美術の最先端だ!
スェーデンで行われたアストリッド・リンドグレーン賞の授賞式で、彼は「ありがとう、アストリッド」という歌を作って、ギターを弾きながらスェーデン語で歌った。
スェーデン人たちは泣いていた。
素晴らしいね!
おみやげ物屋さんで、展覧会の目録と、「えほんのこども」と、絵葉書を5枚買った。
お昼は、サンマルクというベーカリーレストランで食べた。ここが、すごい優秀なの!
スープ、前菜2種、メイン、デザート、飲み物に加えて、なんとパンが食べ放題!
焼きたてのパンを籠に盛ったお姉さんが、しょっちゅうテーブルを回ってきて、好きなだけパンを取らせてくれる。しかも! 一回につき4~5種類のパンがあって、回ってくるたびにパンの種類が違う! ブルーベリーパン、かぼちゃパン、黒ごまチーズパン、野菜パン、ミルクパン、バジルパン、よもぎパン、チョコレートパンetc…
欲張りな私たちは、お腹が破裂しそうなくらいに食べてしまった。
それで、会計は3人で6千円弱!
いっぱい食べた次女のお腹が、膨らんでいた…(わたしもだけど!)
娘たちはふたりとも、ちっさい頃は、ご飯の後はいつも、おなかがぽこっと膨らんでいて、天使みたいだなぁと思っていた。
私は、ふたりの天使と暮らすことができたんだね。幸せな母だね。
そして。
世田谷線で、座っている次女の前に年配のご婦人が立ったとき、次女がそっと立って、席を譲ろうとした。ご婦人は、
「もうすぐ降りるからいいのよ」
と、辞退したのだが、そのとき私は、次女を生んで、ほんとによかったと思った。
アネット・メサジェ : 聖と俗の使者たち
2008年9月23日 芸術
の展覧会を見に、家族4人で森美術館へ行った。
彼女の作品は、一見、キモ・カワ・グロいのだけれど、ヒトや動物や社会の不安定性がそこはかとなく滲み出ている。そういうことに敏感な次女は、早く会場を出たがったので、先に開放してやった。夫とスカイデッキや展望台を散策したとのこと。
長女のほうは逆に、その不安定性の正体を知りたいらしく、会場内を2往復して、丹念に作品を見て回った。見れば見るほど、不安定性とともにある、ユーモアや喜びや悲しみや、恐れ、疑い、嫉妬、生と死、セックスなど、ヒトのあらゆる性質が浮き上がってくるので、離れがたくなる。
私は「カジノ」という作品を、大変気に入り、作品のまん前の特等席で、数十分を過ごした。
お土産物屋さんで、私と長女は、彼女の作品のTシャツを買おうということになったのだが、Sサイズ(私)はあるのに、Mサイズ(長女)が売り切れていた。で、私だけ買った。唇をかみ締める長女。へっ、へっ、へっ、悪いね~。あー、チビでよかった。
お昼は、長女がインド料理を食べたがり、次女は辛いものはイヤだと言う(夫はグルメガイドのロブションを眺めていたが、当然無視される)。私も、気分としてはエスニックだったので、結局、バリスタイルの店に落ち着いた。
帰宅後、夕食時に、展覧会場で流していたフィルムでメサジェが英語を話していたことについて、夫と大喧嘩をした。
「どうせ字幕がつくんだから、下手な英語をしゃべらないで、フランス語を話せばいいと思う。そのほうが細かいニュアンスも伝わるし」(←夫の意見。フランス人独特の傲慢さに満ちた考え方だ)
「世界中の、なるべく多くの人に、通訳を介さず、直接彼女の口からメッセージを伝える手段として、彼女が英語という言語を選んだのは、全く正しい選択だ!」(←私の意見!!正しい!美しい!)
4人で出かけるのって、めんどくさい。
彼女の作品は、一見、キモ・カワ・グロいのだけれど、ヒトや動物や社会の不安定性がそこはかとなく滲み出ている。そういうことに敏感な次女は、早く会場を出たがったので、先に開放してやった。夫とスカイデッキや展望台を散策したとのこと。
長女のほうは逆に、その不安定性の正体を知りたいらしく、会場内を2往復して、丹念に作品を見て回った。見れば見るほど、不安定性とともにある、ユーモアや喜びや悲しみや、恐れ、疑い、嫉妬、生と死、セックスなど、ヒトのあらゆる性質が浮き上がってくるので、離れがたくなる。
私は「カジノ」という作品を、大変気に入り、作品のまん前の特等席で、数十分を過ごした。
お土産物屋さんで、私と長女は、彼女の作品のTシャツを買おうということになったのだが、Sサイズ(私)はあるのに、Mサイズ(長女)が売り切れていた。で、私だけ買った。唇をかみ締める長女。へっ、へっ、へっ、悪いね~。あー、チビでよかった。
お昼は、長女がインド料理を食べたがり、次女は辛いものはイヤだと言う(夫はグルメガイドのロブションを眺めていたが、当然無視される)。私も、気分としてはエスニックだったので、結局、バリスタイルの店に落ち着いた。
帰宅後、夕食時に、展覧会場で流していたフィルムでメサジェが英語を話していたことについて、夫と大喧嘩をした。
「どうせ字幕がつくんだから、下手な英語をしゃべらないで、フランス語を話せばいいと思う。そのほうが細かいニュアンスも伝わるし」(←夫の意見。フランス人独特の傲慢さに満ちた考え方だ)
「世界中の、なるべく多くの人に、通訳を介さず、直接彼女の口からメッセージを伝える手段として、彼女が英語という言語を選んだのは、全く正しい選択だ!」(←私の意見!!正しい!美しい!)
4人で出かけるのって、めんどくさい。
文化祭の振り替え休日を過ごす長女と、BUNKAMURAミュージアムに、ジョン・エヴァレット・ミレイ(1829-96年)の展覧会を見に行った。
地下にある狭い美術館には、見物人がごちゃっと詰まっていた。平日の午前から、皆さんご苦労なこって。
作品はといえば。
なんか、一昔前の少女漫画の世界だなあと思った(いや、実際には少女漫画がこうゆう西洋絵画に影響を受けていたのだろうけど)。
お土産物屋さんで、私たちは、オフィーリアグッズを買いまくった。
「今は旬だから、恥ずくて使えないけど、あと2~3年たって、ほとぼりが冷めた頃に使おう!」と。
お昼は東急本店のDEMIで食べた。デザートプレートの充実ぶり(4種類!)に私たちの目はキラリンと星のようにに輝いた(先程さんざん見た美少女たちのよう?)
そして、スタッフのサービスの連携が素晴らしくよく、気持ちの良い店だった。
地下にある狭い美術館には、見物人がごちゃっと詰まっていた。平日の午前から、皆さんご苦労なこって。
作品はといえば。
なんか、一昔前の少女漫画の世界だなあと思った(いや、実際には少女漫画がこうゆう西洋絵画に影響を受けていたのだろうけど)。
お土産物屋さんで、私たちは、オフィーリアグッズを買いまくった。
「今は旬だから、恥ずくて使えないけど、あと2~3年たって、ほとぼりが冷めた頃に使おう!」と。
お昼は東急本店のDEMIで食べた。デザートプレートの充実ぶり(4種類!)に私たちの目はキラリンと星のようにに輝いた(先程さんざん見た美少女たちのよう?)
そして、スタッフのサービスの連携が素晴らしくよく、気持ちの良い店だった。
身体から発する共通言語
2008年8月31日 芸術を求め、探り、表現するダンス・パフォーマンスを、都内某所で見てきた。
テーマを設定し、経歴も体型も異なる4人の女性ダンサーが、それぞれに、身体を動かし、協調してゆく。
それは即興ではなく、事前に綿密に計算された動きである。
面白くないことはないんだけど…
今ひとつインパクトにかけた。
導入部分の映像は、踊り手も観客も閉じ込められたような空間に、「外」の広がりをもたらす効果がややあって、悪くなかった。
今朝、新聞を呼んでいる私の横で、
「わたしは、オリンピックなんかより断然、パラリンピックを応援する」と、次女が言った。
テーマを設定し、経歴も体型も異なる4人の女性ダンサーが、それぞれに、身体を動かし、協調してゆく。
それは即興ではなく、事前に綿密に計算された動きである。
面白くないことはないんだけど…
今ひとつインパクトにかけた。
導入部分の映像は、踊り手も観客も閉じ込められたような空間に、「外」の広がりをもたらす効果がややあって、悪くなかった。
今朝、新聞を呼んでいる私の横で、
「わたしは、オリンピックなんかより断然、パラリンピックを応援する」と、次女が言った。
コメントをみる | 

君の身体を変換してみよ展
2008年8月29日 芸術
を、オペラシティのNTTインターコミュニケーション・センターに、次女と二人で体験しに行った。
私は、こういう、テクノロジーを使ったインタラクティヴな作品を、面白く感じない。だって、おしなべて、安っぽいんだもん。
技術があるんだから、何とか使わなくちゃという焦りが、そこはかとなく、感じられる。
でも、次女は「全部、おもしろかった!」と、満足なので、これでいいのだ〜(あたしがフランスに行っている間に死んじゃうなんて!赤塚不二夫先生!合掌…)
8歳の次女と、バスを乗り継ぎ、手をつないで出かけた、夏休みの終わり。
お昼は、オペラシティの中にある、とんかつ屋さんの「さぼてん」で、「巻きかつご膳」を食べた。デザートに、黒酢シャーベットという、不思議なものが出てきた。
私は、こういう、テクノロジーを使ったインタラクティヴな作品を、面白く感じない。だって、おしなべて、安っぽいんだもん。
技術があるんだから、何とか使わなくちゃという焦りが、そこはかとなく、感じられる。
でも、次女は「全部、おもしろかった!」と、満足なので、これでいいのだ〜(あたしがフランスに行っている間に死んじゃうなんて!赤塚不二夫先生!合掌…)
8歳の次女と、バスを乗り継ぎ、手をつないで出かけた、夏休みの終わり。
お昼は、オペラシティの中にある、とんかつ屋さんの「さぼてん」で、「巻きかつご膳」を食べた。デザートに、黒酢シャーベットという、不思議なものが出てきた。
コメントをみる | 

長女の演劇部が夏休み期間中に公演をするそうで、彼女が書いた脚本を見せてもらった。
不条理劇なんて見たこと無いはずなのに、なんとも不条理な内容&展開だった。
感想を聞かれたが、良くも悪くもないと、答えておいた。
その昔、大学の文芸学科に通う友人から、卒業のために書いた小説を渡され、感想を書いて欲しいと頼まれた。前衛的なものに対する憧れが強い上に、自意識過剰で、それを洗練された透明感のようなもので包もうとしているので、「あちゃー」と、思った。
でも、私は友達思いなので、
「この作品の作者の持つ、自分と自分以外のものとを計る物差しの目盛りは、意識的にか、無意識的にか、正確なものではない。それは、何かを語る上で、都合がよいとは思えない。」という内容の手紙を送った。
私の手紙のせいではないと思うけれど、彼女は文筆の道に進まなかった。もっと彼女にあった分野を見つけて、試行錯誤しながら活躍している。
長女の脚本を読みながら、このことを思い出した。
幸い、彼女にとって演劇は単なる部活で、目指している職業は全く違う。よかったあ。
不条理劇なんて見たこと無いはずなのに、なんとも不条理な内容&展開だった。
感想を聞かれたが、良くも悪くもないと、答えておいた。
その昔、大学の文芸学科に通う友人から、卒業のために書いた小説を渡され、感想を書いて欲しいと頼まれた。前衛的なものに対する憧れが強い上に、自意識過剰で、それを洗練された透明感のようなもので包もうとしているので、「あちゃー」と、思った。
でも、私は友達思いなので、
「この作品の作者の持つ、自分と自分以外のものとを計る物差しの目盛りは、意識的にか、無意識的にか、正確なものではない。それは、何かを語る上で、都合がよいとは思えない。」という内容の手紙を送った。
私の手紙のせいではないと思うけれど、彼女は文筆の道に進まなかった。もっと彼女にあった分野を見つけて、試行錯誤しながら活躍している。
長女の脚本を読みながら、このことを思い出した。
幸い、彼女にとって演劇は単なる部活で、目指している職業は全く違う。よかったあ。
ニコラ・ド・スタール
2008年6月4日 芸術
南フランスのアンチーブという海沿いの街に、3年半暮らした。
岬の城壁に張り付くように、要塞のような城、グリマルディがあり、そこは、現在、ピカソ美術館として使われている。
その美術館の最上階の、光溢れる静謐な空間で、私はニコラ・ド・スタールに出会い、恋をした。彼の作品と、彼自身に。
色が、形が、浮き上がってきた。色の、形の、配置があまりにも的確なものだから、私はそこに、理想の立体を見た。
日曜の夕方、暇があると、彼の部屋を訪れた。閉館30分前だと、やる気のない受付が、「もーじき閉まるから、タダでいいよ」と、通してくれた。
そうだよ。恋人との短い逢瀬に、金は要らないぜ?
彼は、1955年、41歳のとき、グリマルディの近くの海に面したアトリエの窓から身を投げた。
そのことについて詳しく調べて考えると、こちらの精神が危うくなりそうなので、あえてその辺は避けて。
ひたすらに作品と向き合い、作品に圧倒され、作品に入っていった。
今、私の台所には、白い額縁に入った蒼い静物画が置いてあって、私は彼と一緒に暮らしている。
岬の城壁に張り付くように、要塞のような城、グリマルディがあり、そこは、現在、ピカソ美術館として使われている。
その美術館の最上階の、光溢れる静謐な空間で、私はニコラ・ド・スタールに出会い、恋をした。彼の作品と、彼自身に。
色が、形が、浮き上がってきた。色の、形の、配置があまりにも的確なものだから、私はそこに、理想の立体を見た。
日曜の夕方、暇があると、彼の部屋を訪れた。閉館30分前だと、やる気のない受付が、「もーじき閉まるから、タダでいいよ」と、通してくれた。
そうだよ。恋人との短い逢瀬に、金は要らないぜ?
彼は、1955年、41歳のとき、グリマルディの近くの海に面したアトリエの窓から身を投げた。
そのことについて詳しく調べて考えると、こちらの精神が危うくなりそうなので、あえてその辺は避けて。
ひたすらに作品と向き合い、作品に圧倒され、作品に入っていった。
今、私の台所には、白い額縁に入った蒼い静物画が置いてあって、私は彼と一緒に暮らしている。
四谷へ。
身体表現を追及している人たちの、公開練習を見に行った。
Nの動きが、素晴らしかった。別役実の童話の朗読と身体の動きが完全に親和して、空間全体が異次元にシフトしたと感じた。私たちをとりまく空気の粒子の一粒一粒が、性質を変えた時間だった。
Nは、いつも丁寧に自分の体と付き合い、可能性を突き詰め、表現方法を探っている。恐るべき集中力で、全てをおろそかにせず。神経の隅々にまで、気合を込めて。
そういう人を、芸術の神様はちゃんと掬い上げてくれるのである。
身体表現を追及している人たちの、公開練習を見に行った。
Nの動きが、素晴らしかった。別役実の童話の朗読と身体の動きが完全に親和して、空間全体が異次元にシフトしたと感じた。私たちをとりまく空気の粒子の一粒一粒が、性質を変えた時間だった。
Nは、いつも丁寧に自分の体と付き合い、可能性を突き詰め、表現方法を探っている。恐るべき集中力で、全てをおろそかにせず。神経の隅々にまで、気合を込めて。
そういう人を、芸術の神様はちゃんと掬い上げてくれるのである。
舞踏は、「詩」を舞台芸術に置き換えたものだと、つねづね思っていた。
そして最近、舞踏家と詩人には妙な共通性があることに気付き始めた。
誰もが土方巽や大野一雄になれないように、誰もが中原中也やランボーやディキンスンにはなれない。
そこのところを、意識的にか、無意識的にか、理解する過程をすっ飛ばして、才能のない輩が自らを「舞踏家」「詩人」と称して、活動を繰り広げる。自意識ばかりがあふれ出る、鑑賞に耐えないものを作品と称して、発表し続ける。
なぜ、このようなことが起きるのかと考えてみると、舞踏家と詩人は、いずれにしても職業として成り立たない分野だからかもしれないという結論に至る。
舞踏、もしくは詩のみを生業としている人は、いないだろう。
才能があって、評価が高くたって、アマチュアなのだ。
だから、才能がなくて、誰にも認められていなくても、自分で名乗りさえすればその瞬間から、舞踏家になり、詩人になれる。
一見、伝統的なテクニックの修練を積まなくてもできちゃいそうなそうなところも、自意識過剰な表現したがり屋さんには、手軽でよいのかもしれない。何しろ、両分野とも、「前衛」であることが身上ですもの。
あははははは。
しかしながら!
舞踏家と詩人には、大きな違いがあることはある。
それは、舞踏家はおおむね長生きで、詩人は早世する傾向にあるということだ。
やっぱり、ヒトって、長持ちさせるためには、体を動かさなきゃだめらしい。
本日は次女の小学校にて、常任委員会・校外委員会に出席。つまらない会合に出ると、ついこんなことを、つらつらと考えてしまう!
そして最近、舞踏家と詩人には妙な共通性があることに気付き始めた。
誰もが土方巽や大野一雄になれないように、誰もが中原中也やランボーやディキンスンにはなれない。
そこのところを、意識的にか、無意識的にか、理解する過程をすっ飛ばして、才能のない輩が自らを「舞踏家」「詩人」と称して、活動を繰り広げる。自意識ばかりがあふれ出る、鑑賞に耐えないものを作品と称して、発表し続ける。
なぜ、このようなことが起きるのかと考えてみると、舞踏家と詩人は、いずれにしても職業として成り立たない分野だからかもしれないという結論に至る。
舞踏、もしくは詩のみを生業としている人は、いないだろう。
才能があって、評価が高くたって、アマチュアなのだ。
だから、才能がなくて、誰にも認められていなくても、自分で名乗りさえすればその瞬間から、舞踏家になり、詩人になれる。
一見、伝統的なテクニックの修練を積まなくてもできちゃいそうなそうなところも、自意識過剰な表現したがり屋さんには、手軽でよいのかもしれない。何しろ、両分野とも、「前衛」であることが身上ですもの。
あははははは。
しかしながら!
舞踏家と詩人には、大きな違いがあることはある。
それは、舞踏家はおおむね長生きで、詩人は早世する傾向にあるということだ。
やっぱり、ヒトって、長持ちさせるためには、体を動かさなきゃだめらしい。
本日は次女の小学校にて、常任委員会・校外委員会に出席。つまらない会合に出ると、ついこんなことを、つらつらと考えてしまう!