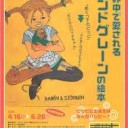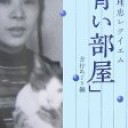死刑 人は人を殺せる。でも人は、人を救いたいとも思う
2011年10月22日 読書
もちろん、私は「死刑廃止派」だ。たとえ家族が殺されたって、犯人に死刑を!とは叫ばないだろう。
理由はいくつもあるけれど(冤罪の可能性とか、犯罪の抑止力があるとは思えないとか)、一番の理由は生理的に厭だから。死刑が。
森さんは、本書の執筆のために、取材する。死刑囚、元死刑囚、被害者の家族、刑務官、教誨師、弁護士らにインタビューを重ね、考える。そしていちいち、素直に悩む。
思考のロードムービーだ。
たどりつく彼の結論は、「廃止」。
もともと廃止よりだったのだが、悩みを積み重ねた末の、感情むき出しの叫び。
だから逆に。
日本やアメリカで死刑が存置しているというのは、論理とか倫理とかのレベルではなくて、ただ「生理的」「感情的に」にそれを望んでいる人たちが多いってことなんだなあと、妙な具合に納得した。生理・感情的にそれを望んでいる人たちの主張を論破するのは、不可能だもの。
理由はいくつもあるけれど(冤罪の可能性とか、犯罪の抑止力があるとは思えないとか)、一番の理由は生理的に厭だから。死刑が。
森さんは、本書の執筆のために、取材する。死刑囚、元死刑囚、被害者の家族、刑務官、教誨師、弁護士らにインタビューを重ね、考える。そしていちいち、素直に悩む。
思考のロードムービーだ。
たどりつく彼の結論は、「廃止」。
もともと廃止よりだったのだが、悩みを積み重ねた末の、感情むき出しの叫び。
だから逆に。
日本やアメリカで死刑が存置しているというのは、論理とか倫理とかのレベルではなくて、ただ「生理的」「感情的に」にそれを望んでいる人たちが多いってことなんだなあと、妙な具合に納得した。生理・感情的にそれを望んでいる人たちの主張を論破するのは、不可能だもの。
に行った。カデットと。
展示してあるのは、各国の画家による挿絵。
興味深いけれど、すごく面白いというわけでもなく。
一番好きだったのは、日本人の桜井誠。
スェーデン人の原画を意識して描いたそうだが、
いま見てもグッとくる、いかしたセンス。
時間があったので、一時間余りをライブラリーで過ごした。
文学館の目録2冊「父からの贈りもの 森鴎外と娘たち」
と、「堀内誠一 旅と絵本とデザインと」を熟読した。
カデットには、リンドグレーンの処女作「ブリット・マリはただいま幸せ」を買った。
エネは、ワークショップで知り合った友達と、岡本太郎展へ行った。
夫は、オンワードの社販へ行って、ワイシャツ2枚とスーツ一着を買った。
展示してあるのは、各国の画家による挿絵。
興味深いけれど、すごく面白いというわけでもなく。
一番好きだったのは、日本人の桜井誠。
スェーデン人の原画を意識して描いたそうだが、
いま見てもグッとくる、いかしたセンス。
時間があったので、一時間余りをライブラリーで過ごした。
文学館の目録2冊「父からの贈りもの 森鴎外と娘たち」
と、「堀内誠一 旅と絵本とデザインと」を熟読した。
カデットには、リンドグレーンの処女作「ブリット・マリはただいま幸せ」を買った。
エネは、ワークショップで知り合った友達と、岡本太郎展へ行った。
夫は、オンワードの社販へ行って、ワイシャツ2枚とスーツ一着を買った。
長女の部屋に転がっていたので、拾い上げて読んでみた。
彼女が学校の図書室で借りた本である。
人物の性格設定がステレオタイプなので、笑ってしまった。
結末に向かって作品が失速してゆくのが、なんとも歯がゆい。
第1章のテンションと強気姿勢で最後まで突っ走ったら、もっと迷作になったのに!
これを読んで以来、長女に注意をするとき、
「牛乳に何か入れるよ!?」
と、最後に付け足すようになった。
小説よりブラックな家庭である。
彼女が学校の図書室で借りた本である。
人物の性格設定がステレオタイプなので、笑ってしまった。
結末に向かって作品が失速してゆくのが、なんとも歯がゆい。
第1章のテンションと強気姿勢で最後まで突っ走ったら、もっと迷作になったのに!
これを読んで以来、長女に注意をするとき、
「牛乳に何か入れるよ!?」
と、最後に付け足すようになった。
小説よりブラックな家庭である。
まんが パレスチナ問題 (講談社現代新書)
2009年7月14日 読書 コメント (3)
私がパレスチナを支援しているのを知って、何人かの友人が、この本を買った。
イスラエルとパレスチナの歴史と現状を知ろうと思うとき、入門書として一番手に取りやすいのだろう。
著者は、おおむね、公平な立ち位置で書いていると思う。
だけど!!!!
アラファト議長のダークサイドばかり強調して、彼の功績を無視しているところが気に入らない!
彼は、決して、金の亡者ではなかった。確かに資金援助の引き出し方は巧妙だったけど、彼が個人的に使った金なんて、一銭もない。全ては、PLOのため。
イスラエルに何ヶ月も軟禁され、兵粮攻にあったって、
「普段からろくなもの食べてないから、へっちゃらだよ」
って、涼しい顔をしていた。
軍服しかきないから、洋服代もかからなかった。
フランスのドキュメンタリーで見た彼の自宅は、広いけれど質素で、親を殺された孤児を大勢引き取って育てていた。
せっかくアラファト議長が武装闘争の禁止令を出して、実際に3週間ほどテロが止んでいたのに、イスラエル軍が議長の側近(武闘派)を暗殺してしまったせいで、泥沼の自爆テロが再開したことに触れていないのも気に入らない
だれか、アラファト議長を正当に評価できる人が、彼の評伝を書いてくれないかしら。
イスラエルとパレスチナの歴史と現状を知ろうと思うとき、入門書として一番手に取りやすいのだろう。
著者は、おおむね、公平な立ち位置で書いていると思う。
だけど!!!!
アラファト議長のダークサイドばかり強調して、彼の功績を無視しているところが気に入らない!
彼は、決して、金の亡者ではなかった。確かに資金援助の引き出し方は巧妙だったけど、彼が個人的に使った金なんて、一銭もない。全ては、PLOのため。
イスラエルに何ヶ月も軟禁され、兵粮攻にあったって、
「普段からろくなもの食べてないから、へっちゃらだよ」
って、涼しい顔をしていた。
軍服しかきないから、洋服代もかからなかった。
フランスのドキュメンタリーで見た彼の自宅は、広いけれど質素で、親を殺された孤児を大勢引き取って育てていた。
せっかくアラファト議長が武装闘争の禁止令を出して、実際に3週間ほどテロが止んでいたのに、イスラエル軍が議長の側近(武闘派)を暗殺してしまったせいで、泥沼の自爆テロが再開したことに触れていないのも気に入らない
だれか、アラファト議長を正当に評価できる人が、彼の評伝を書いてくれないかしら。
子供の頃、家にあった昭和文学全集の中の獅子文六集を、夢中になって読んだ。
旧仮名遣いで細かい文字の2段にもかかわらず、あまりの面白さにのめり込んだ。
そこに載っていない作品は、古本屋で二束三文で売られていたので、お小遣いで買って読みまくった。
獅子文六が書くものは、どうにもこうにも、「昭和」である。暮らしの手帖の第1世紀の「昭和」である。
私は「昭和」生まれの「昭和」育ち。
「平成」に変わったときはパリで暮らしていたので、その変化が身に沁みていなくて、いつまでたっても「昭和」気分だ。
数年前、友人Nに、獅子文六の本を勧めた。彼女は私より若いけれど「昭和」好きなので、気に入るんじゃないかと思ったら、ちょーハマッタ。ついでに古本の世界にも足を踏み入れた。鼻息荒くして!
やがて、昭和の文学も古典の一部になるだろう(もーなってるか?)。でも、獅子文六の作品はいわゆる文学的な評価の高いものではないから、古典として残ることはないだろう。
それでも、一部のマニアに、細々と読み継がれていったらいいなぁと思う。
旧仮名遣いで細かい文字の2段にもかかわらず、あまりの面白さにのめり込んだ。
そこに載っていない作品は、古本屋で二束三文で売られていたので、お小遣いで買って読みまくった。
獅子文六が書くものは、どうにもこうにも、「昭和」である。暮らしの手帖の第1世紀の「昭和」である。
私は「昭和」生まれの「昭和」育ち。
「平成」に変わったときはパリで暮らしていたので、その変化が身に沁みていなくて、いつまでたっても「昭和」気分だ。
数年前、友人Nに、獅子文六の本を勧めた。彼女は私より若いけれど「昭和」好きなので、気に入るんじゃないかと思ったら、ちょーハマッタ。ついでに古本の世界にも足を踏み入れた。鼻息荒くして!
やがて、昭和の文学も古典の一部になるだろう(もーなってるか?)。でも、獅子文六の作品はいわゆる文学的な評価の高いものではないから、古典として残ることはないだろう。
それでも、一部のマニアに、細々と読み継がれていったらいいなぁと思う。
さすらいの孤児ラスムス (岩波少年文庫)
2009年6月15日 読書
次女図書館(彼女が自分の部屋で開いている図書館)で、借りた。司書さん(次女)のお勧めだったので。
海辺の廃屋を、ラスムスとオスカルが見つけるときの描写が、実に、実に、素晴らしい。
わたしまで、放浪の旅に出たくなってしまうではないか!
リンドグレーンは、驚くべきことに、作品によって、作風も世界観も全く様変わりする。
『長くつ下のピッピ』シリーズと、『やかまし村の子どもたち』シリーズと、『ちいさいロッタちゃん』シリーズが同じ作者なのは、まだうなずける。
でも!
『さすらいの孤児ラスムス』の人生観!
『ミオよ、わたしのミオ』の、ファンタジーというジャンルを軽く超えた想像力!
とても同一人物が書いたとは思えない。
日本には、こんなに才能豊かな児童文学作家はいないなぁ。
海辺の廃屋を、ラスムスとオスカルが見つけるときの描写が、実に、実に、素晴らしい。
わたしまで、放浪の旅に出たくなってしまうではないか!
リンドグレーンは、驚くべきことに、作品によって、作風も世界観も全く様変わりする。
『長くつ下のピッピ』シリーズと、『やかまし村の子どもたち』シリーズと、『ちいさいロッタちゃん』シリーズが同じ作者なのは、まだうなずける。
でも!
『さすらいの孤児ラスムス』の人生観!
『ミオよ、わたしのミオ』の、ファンタジーというジャンルを軽く超えた想像力!
とても同一人物が書いたとは思えない。
日本には、こんなに才能豊かな児童文学作家はいないなぁ。
日本の知の巨人、加藤周一が去年の暮れに亡くなった。
私は朝日新聞の夕陽妄語を愛読していた。
先日NHKで、彼をを偲ぶ、10分ほどの番組があった。
秋葉通り魔事件に関して、こう発言していた。死の、半年前である。
「内的に彼らの心理がわかるというのではないが、全然何もない(ところへ)、天から降ったという気はしないな。やはり、下の方によどんでいたものが急に爆発した、小さな絶望的爆発ですね」
今は、よどんでいるものを、澄んだものに変えなければならないときなのに、実際は逆の方向に向かっている。よどんだものが、より多く、より分厚く、蓄積している。
政治家も官僚も、目先にとらわれ、本質的な問題を理解しようとはしていない。
というか、彼らは、保身に忙しすぎて、「本質的な問題を理解して解決することに頭を使う」余裕が、精神的にも時間的にもなくて、またその能力もないのだ。
要するに、資質にかけた人々が、政治家や官僚になっているのよね?
日本人は、比較的穏やかで、慎み深く、我慢強い性質を持つので、弱いものをどこまでも虐げたって平気だと感じているのだろう。(ちょっとなんか不満があっただけで、デモをしたりストをしたりする某国とは大違い!←フランスのことだけど!)
けれど、それにも限界があるだろう。
「小さな絶望的爆発」は、数を増し、規模を大きくするのではないか?
だいいち、多くの人々が絶望を感じながら生きている国って、どうなのよ?
それにしても、若いときの加藤周一って、もんのすごいイイ男。
とりあえず、『日本文学史序説』読も。
私は朝日新聞の夕陽妄語を愛読していた。
先日NHKで、彼をを偲ぶ、10分ほどの番組があった。
秋葉通り魔事件に関して、こう発言していた。死の、半年前である。
「内的に彼らの心理がわかるというのではないが、全然何もない(ところへ)、天から降ったという気はしないな。やはり、下の方によどんでいたものが急に爆発した、小さな絶望的爆発ですね」
今は、よどんでいるものを、澄んだものに変えなければならないときなのに、実際は逆の方向に向かっている。よどんだものが、より多く、より分厚く、蓄積している。
政治家も官僚も、目先にとらわれ、本質的な問題を理解しようとはしていない。
というか、彼らは、保身に忙しすぎて、「本質的な問題を理解して解決することに頭を使う」余裕が、精神的にも時間的にもなくて、またその能力もないのだ。
要するに、資質にかけた人々が、政治家や官僚になっているのよね?
日本人は、比較的穏やかで、慎み深く、我慢強い性質を持つので、弱いものをどこまでも虐げたって平気だと感じているのだろう。(ちょっとなんか不満があっただけで、デモをしたりストをしたりする某国とは大違い!←フランスのことだけど!)
けれど、それにも限界があるだろう。
「小さな絶望的爆発」は、数を増し、規模を大きくするのではないか?
だいいち、多くの人々が絶望を感じながら生きている国って、どうなのよ?
それにしても、若いときの加藤周一って、もんのすごいイイ男。
とりあえず、『日本文学史序説』読も。
キルプの軍団 (講談社文庫)
2009年3月25日 読書
ディケンズの「骨董屋」を読み進めがら、刑事の忠叔父さん&小説家の父親に見守られつつ、未知の人々に出会い、未知の体験をしていく、高校生の男の子、オーちゃんの成長物語。
ストーリーの後半は正直、取ってつけたような、身も蓋もないような展開だ。
でも、オーちゃんの内面の描き方が優れていて、オーちゃんの物事に対する見方や、思考の過程には納得させられることが多かった。これって、あたしの精神状態が思春期なせい?
そして、個人的に忘れることのないであろう本となった。
なぜなら。
私は、文庫本は主に電車での移動中に読むわけだが。
ある日、新宿へ行くために渋谷からJRに乗り、この本に没頭していると、すぐ目の前から、聞き覚えのある声がしてきて、ふと顔を上げると、知り合いのご婦人がいた。久しぶりだったので、驚きとともに再会を喜びつつ、世間話をし始めたのだが、物語世界に浸かっていた私はなかなか現実世界に戻れず、共通の知人の名前が、出てこないのだった。すると彼女は、
「大江健三郎の本にのめり込んでいたんだもん、しょうがないわよ」
と、真面目な顔でおっしゃった。
大江本をむき出しで読むことが急に恥ずかしくなった私は(まるで女子高生だね)、その日、ブックカバーを買って、この本に着せてやった。
先週亡くなったのは、彼女のご主人だ。
そして。
この主人公オーちゃんは成城学園に住んでいて、たびたび小田急線に乗る。母が入院していたとき、私は成城学園にも止まる小田急線の急行に乗り、病院へ通った。車中でページをめぐりながら、現実と物語がシンクロして、めまいを感じた。
物語とともに、実際に私の心と身体も移動する、風変わりな読書体験であった。
ずっと私は、大江健三郎に対してはニュートラルな気持ちしか抱いていなかったのだが、おととし、パレスチナの知の巨人、故エドワード・サイードのドキュメンタリー映画の上映会に行ったら、大江の講演があり、サイードへの理解と親しみが深く感じられ、それ以来ちょっとした好感を持っている。
あさって、私はこの本を、友人Nに返す。さよならだね。
ストーリーの後半は正直、取ってつけたような、身も蓋もないような展開だ。
でも、オーちゃんの内面の描き方が優れていて、オーちゃんの物事に対する見方や、思考の過程には納得させられることが多かった。これって、あたしの精神状態が思春期なせい?
そして、個人的に忘れることのないであろう本となった。
なぜなら。
私は、文庫本は主に電車での移動中に読むわけだが。
ある日、新宿へ行くために渋谷からJRに乗り、この本に没頭していると、すぐ目の前から、聞き覚えのある声がしてきて、ふと顔を上げると、知り合いのご婦人がいた。久しぶりだったので、驚きとともに再会を喜びつつ、世間話をし始めたのだが、物語世界に浸かっていた私はなかなか現実世界に戻れず、共通の知人の名前が、出てこないのだった。すると彼女は、
「大江健三郎の本にのめり込んでいたんだもん、しょうがないわよ」
と、真面目な顔でおっしゃった。
大江本をむき出しで読むことが急に恥ずかしくなった私は(まるで女子高生だね)、その日、ブックカバーを買って、この本に着せてやった。
先週亡くなったのは、彼女のご主人だ。
そして。
この主人公オーちゃんは成城学園に住んでいて、たびたび小田急線に乗る。母が入院していたとき、私は成城学園にも止まる小田急線の急行に乗り、病院へ通った。車中でページをめぐりながら、現実と物語がシンクロして、めまいを感じた。
物語とともに、実際に私の心と身体も移動する、風変わりな読書体験であった。
ずっと私は、大江健三郎に対してはニュートラルな気持ちしか抱いていなかったのだが、おととし、パレスチナの知の巨人、故エドワード・サイードのドキュメンタリー映画の上映会に行ったら、大江の講演があり、サイードへの理解と親しみが深く感じられ、それ以来ちょっとした好感を持っている。
あさって、私はこの本を、友人Nに返す。さよならだね。
小高へ 父 島尾敏雄への旅
2008年11月14日 読書 コメント (4)
島尾ミホの『海辺の生と死』は、女性文学の傑作だと思っている。
彼女の書くものは、常軌を逸するまでに美しく、純粋で、優しさと愛に溢れている。
だから。
島尾敏雄の『死の棘』では、「精神病の奥さん」となり、島尾伸三の著書では、「頭のおかしいお母さん」ということになる。
ようするに、そういうことなのだろう。
島尾伸三は、両親を憎んでいるが、(本人が嫌々書いている)その文章を読むと、まさしく敏雄とミホの子だ。
二人の文学のセンスが混じり合っている。
しかしながら、幸いなることに、彼の作品には、親より優れている部分が多々ある。
自らの狂気を自覚しているところ、絶望の先に光が感じられるところ、ユーモアがあるところ、写真が非常に美しいところ(写真家だから、当たり前っちゃあ、当たり前だけど)など。
それにしても!!
私がこの本を手に入れるのにどんなに苦労したか。
10月12日の朝日新聞の「著者に会いたい」というコラムで、大々的に紹介されていたので、渋谷の紀伊国屋へ行って検索すると、「在庫なし」。次の週も、そのまた次の週も「在庫なし」。新宿の紀伊国屋(南口のビル丸ごと本屋)に行って検索したら、やっと「在庫あり」。しかし、印刷した紙を持って売り場を探すが見つからず。店員に聞くと、「売り切れました。注文も予約も出来ません」だと!!
新聞で紹介された本が、巨大書店で手に入らないって、どーゆーこと?
新聞の書評欄を見るたびに、日本人ってインテリだなあと思うんだけど、本屋に行って平積みされている本を見ると、日本人って、レベルが低いなあと思う。このギャップは、いったい何なんだ?
結局、この本は、ネット書店で手に入れましたとさ。
彼女の書くものは、常軌を逸するまでに美しく、純粋で、優しさと愛に溢れている。
だから。
島尾敏雄の『死の棘』では、「精神病の奥さん」となり、島尾伸三の著書では、「頭のおかしいお母さん」ということになる。
ようするに、そういうことなのだろう。
島尾伸三は、両親を憎んでいるが、(本人が嫌々書いている)その文章を読むと、まさしく敏雄とミホの子だ。
二人の文学のセンスが混じり合っている。
しかしながら、幸いなることに、彼の作品には、親より優れている部分が多々ある。
自らの狂気を自覚しているところ、絶望の先に光が感じられるところ、ユーモアがあるところ、写真が非常に美しいところ(写真家だから、当たり前っちゃあ、当たり前だけど)など。
それにしても!!
私がこの本を手に入れるのにどんなに苦労したか。
10月12日の朝日新聞の「著者に会いたい」というコラムで、大々的に紹介されていたので、渋谷の紀伊国屋へ行って検索すると、「在庫なし」。次の週も、そのまた次の週も「在庫なし」。新宿の紀伊国屋(南口のビル丸ごと本屋)に行って検索したら、やっと「在庫あり」。しかし、印刷した紙を持って売り場を探すが見つからず。店員に聞くと、「売り切れました。注文も予約も出来ません」だと!!
新聞で紹介された本が、巨大書店で手に入らないって、どーゆーこと?
新聞の書評欄を見るたびに、日本人ってインテリだなあと思うんだけど、本屋に行って平積みされている本を見ると、日本人って、レベルが低いなあと思う。このギャップは、いったい何なんだ?
結局、この本は、ネット書店で手に入れましたとさ。
私の絵日記 (学研M文庫)
2008年10月28日 読書 コメント (2)
私の、超・愛読書。
藤原マキ(1941-1999)は、つげ義春の奥さんであり、かつて状況劇場の女優でもあった人。
昨日の新聞の書評欄で、つげ義春コレクションの第一回(ねじ式・夜が掴む)が配本になったという記事を読んで、久しぶりにこの本を、引っ張り出した。
この本の中では、彼女自身が残しておきたかった思い出が、工夫を凝らして描かれている。
そして、巻末の長いインタビューでつげ義春が語る、夫から見た妻の姿が、その思い出を補足している。
絵も、文章も、すごくイイ。
のどの奥をきゅうっと締め付けられるような、泣きたいけど泣かないときの気持ちになる。
彼女のスケッチした、つげ義春の寝顔は、見るたびに胸を突かれる。
写真にうつる彼女は、ことごとく満面の笑顔だ。だから、切なくなるのは、彼女の本意ではないだろうと、本を開くたび、自分に言い聞かせる。
藤原マキ(1941-1999)は、つげ義春の奥さんであり、かつて状況劇場の女優でもあった人。
昨日の新聞の書評欄で、つげ義春コレクションの第一回(ねじ式・夜が掴む)が配本になったという記事を読んで、久しぶりにこの本を、引っ張り出した。
この本の中では、彼女自身が残しておきたかった思い出が、工夫を凝らして描かれている。
そして、巻末の長いインタビューでつげ義春が語る、夫から見た妻の姿が、その思い出を補足している。
絵も、文章も、すごくイイ。
のどの奥をきゅうっと締め付けられるような、泣きたいけど泣かないときの気持ちになる。
彼女のスケッチした、つげ義春の寝顔は、見るたびに胸を突かれる。
写真にうつる彼女は、ことごとく満面の笑顔だ。だから、切なくなるのは、彼女の本意ではないだろうと、本を開くたび、自分に言い聞かせる。
私は、島尾敏雄と島尾ミホの「死の棘」カップルのファンだ。
今朝の新聞に、息子で写真家の島尾伸三が最近出した、「小高へ 父 島尾敏雄への旅」(河出書房新社)という本についての記事が載っていて、無性に島尾伸三の本が読みたくなった。
それで、午後、図書館へ行くという長女に、
「何でもいいから、島尾伸三の本を借りてきて」
と、頼んだ。最新作は望めなくても、以前の著作が読めたらいいなあと、思ったのだ。
そして。
帰宅した長女が差し出したのが、この本だ。
「????????????」
頭の中が?マークだらけになったよ?
「だって、検索したら、これしかなかったんだもん。他の本は、全部借りられちゃってたんだもん」
それにしても…・
中を開くと、確かに、島尾伸三のエッセイが4ページあった。それは、義理のお母さんが靖国神社の近くの女学校に通っていたというエピソードが半分と、遊就館に関しての軽い感想文で、確かに島尾伸三らしい文章ではあったのだけれど、何故にこの人がこの本に寄稿するのか、さっぱりその理由がわからなかった。
しかしながら。
この本の内容はと言えば、そりゃあもう、思想的に偏りがあるのはもちろんなのだが、(だって、サブタイトルが、「首相の公式参拝を批判する入門書」だもんね)、姜尚中と高橋哲哉の対談があるかと思えば、1939年「主婦の友」6月号掲載の「母一人子一人の愛児を御国に捧げた 誉れの母の感涙座談会」なんてものがあったりして、興味深くない、ことはない。
ので、ついつい熟読しちゃったりして、ああ、あたし、ダイジョブかしら?
ちなみにこれ、2006年発行だけど、長女が最初の借り出し者だと思う。だって、まっさらの新品状態だもん。良かったね、借りてもらえて。
最近、ワタシの上には、妙な読書の神様が降臨しているよーだ。
と思いつつ。
読んでいくうちに思い出したよ。
母が丹波で疎開していた頃の友人が去年、初めて、東京へ来たときのこと。
「どこへ行きたい?」と聞いたら、
「靖国神社!!」というので、連れて行ったんだって。
友人は、一日中、隅から隅まで靖国を堪能して、
「生きているうちに来ることが出来てよかった」って、涙を流したんだって。
もしかしたらワタシ、入門よりもっと深いところに足を突っ込んじゃうかもしれません…
今朝の新聞に、息子で写真家の島尾伸三が最近出した、「小高へ 父 島尾敏雄への旅」(河出書房新社)という本についての記事が載っていて、無性に島尾伸三の本が読みたくなった。
それで、午後、図書館へ行くという長女に、
「何でもいいから、島尾伸三の本を借りてきて」
と、頼んだ。最新作は望めなくても、以前の著作が読めたらいいなあと、思ったのだ。
そして。
帰宅した長女が差し出したのが、この本だ。
「????????????」
頭の中が?マークだらけになったよ?
「だって、検索したら、これしかなかったんだもん。他の本は、全部借りられちゃってたんだもん」
それにしても…・
中を開くと、確かに、島尾伸三のエッセイが4ページあった。それは、義理のお母さんが靖国神社の近くの女学校に通っていたというエピソードが半分と、遊就館に関しての軽い感想文で、確かに島尾伸三らしい文章ではあったのだけれど、何故にこの人がこの本に寄稿するのか、さっぱりその理由がわからなかった。
しかしながら。
この本の内容はと言えば、そりゃあもう、思想的に偏りがあるのはもちろんなのだが、(だって、サブタイトルが、「首相の公式参拝を批判する入門書」だもんね)、姜尚中と高橋哲哉の対談があるかと思えば、1939年「主婦の友」6月号掲載の「母一人子一人の愛児を御国に捧げた 誉れの母の感涙座談会」なんてものがあったりして、興味深くない、ことはない。
ので、ついつい熟読しちゃったりして、ああ、あたし、ダイジョブかしら?
ちなみにこれ、2006年発行だけど、長女が最初の借り出し者だと思う。だって、まっさらの新品状態だもん。良かったね、借りてもらえて。
最近、ワタシの上には、妙な読書の神様が降臨しているよーだ。
と思いつつ。
読んでいくうちに思い出したよ。
母が丹波で疎開していた頃の友人が去年、初めて、東京へ来たときのこと。
「どこへ行きたい?」と聞いたら、
「靖国神社!!」というので、連れて行ったんだって。
友人は、一日中、隅から隅まで靖国を堪能して、
「生きているうちに来ることが出来てよかった」って、涙を流したんだって。
もしかしたらワタシ、入門よりもっと深いところに足を突っ込んじゃうかもしれません…
午前中、夫が寝室やリビングの本棚をごそごそやっている。しばらくして、ニコニコしながら、
「2冊見つけた!」
ル・クレジオの、「Le Chercheur d’Or(黄金探索者)」と、「Hasard : suivi d’Angoli Mala (偶然 帆船アザールの冒険)」である。
「『Le Chercheur d’Or』は、読んだの覚えているけど、『Hasard : suivi d’Angoli Mala』は、読んだ覚えないなあ…」
「だって、それ、あたしが買ったんだよ?」
「あ、そうだったのかー。じゃ、読んでみるよ。君、『Le Chercheur d’Or』、まだ読んでなかったら、読んでみれば?」
なんで、ノーベル文学賞を取ったからって、突然、ル・クレジオを読まなきゃならないの?私には、夫のミーハー心が理解できない。
それにしても。
つくづく、村上春樹が取らなくて良かったなあと思う。だって、もしも彼が取ったら、日本中大騒ぎで、鬱陶しくてかなわないだろう。本屋は彼の本で埋め尽くされて、相対的に、私の読みたい本の置かれる面積が(ただですら少ないのに)、ますます少なくなるではないか?
きっと、ご本人だって、そういうお祭り騒ぎは好きではないのでは?
それなのに夫、
「来年はムラカミが取ればいいのに」
だって!(ハルキ・ムラカミ作品は、たくさん仏訳されていて、夫は、彼のファンで、周りのフランス人にも勧めまくっている)
もー!!
離婚しようかしら?
「2冊見つけた!」
ル・クレジオの、「Le Chercheur d’Or(黄金探索者)」と、「Hasard : suivi d’Angoli Mala (偶然 帆船アザールの冒険)」である。
「『Le Chercheur d’Or』は、読んだの覚えているけど、『Hasard : suivi d’Angoli Mala』は、読んだ覚えないなあ…」
「だって、それ、あたしが買ったんだよ?」
「あ、そうだったのかー。じゃ、読んでみるよ。君、『Le Chercheur d’Or』、まだ読んでなかったら、読んでみれば?」
なんで、ノーベル文学賞を取ったからって、突然、ル・クレジオを読まなきゃならないの?私には、夫のミーハー心が理解できない。
それにしても。
つくづく、村上春樹が取らなくて良かったなあと思う。だって、もしも彼が取ったら、日本中大騒ぎで、鬱陶しくてかなわないだろう。本屋は彼の本で埋め尽くされて、相対的に、私の読みたい本の置かれる面積が(ただですら少ないのに)、ますます少なくなるではないか?
きっと、ご本人だって、そういうお祭り騒ぎは好きではないのでは?
それなのに夫、
「来年はムラカミが取ればいいのに」
だって!(ハルキ・ムラカミ作品は、たくさん仏訳されていて、夫は、彼のファンで、周りのフランス人にも勧めまくっている)
もー!!
離婚しようかしら?
仕事関係の本以外は、自分の好きな本ばかりをずっと読んで過ごしてきた。
さっき、mixiのプロフィールを見たら、私の好きな本は、「吉行理恵 島尾ミホ ジュヌヴィエーヴ・ブリザック フラナリー・オコナー エミリー・ディキンスン 久生十蘭 深沢七郎」なんだって(なんだってって、自分が書いたプロフィールだろ?って感じだけど、何年も前に書いたんだもん)。
それ以外のものだってもちろん読んでいたけれど、まあ、そういう、偏りのある読書傾向だったのだ。
しかし、最近は、友人たちが私に、(有無をも言わさず)いろんな本を貸してくれる。直接手渡されることはもちろんだが、ウチの前を通りかかるたびに、お勧め本をポストに放り込んでいく人もいるし、宅急便で送ってくる人までいる。
おまけに。
本好きの長女が、これまたお勧めの本を「読め読め」と、迫ってくる。彼女が貸してくれる本は、彼女が図書館で借りてきた本なので、さっさと読んで返さなければならない。彼女は、自由に本を買えるほどお小遣いを与えられていないので、4枚の図書館カード(住んでいる区の図書館、学校のある区の図書館、学校の中等部の図書館と高等部の図書館)を駆使して、大量の本を借りてくるのだ。
そんなわけで。
私の机の上には、読まなければならない本が、山積みになっている。私は、自分の趣味とは全く異なる本を、苦行のように(?)せっせと読んでいる。つまんなくても、我慢して読んでいる。これで、私の世界は広がるんだろーか?
(商品レビューにあるのは、「中学生の気持ちが知りたかったら、コレ読んで!」と、さっき長女に押し付けられて、半分程、読んだ本。別に、中学生の気持ちなんか、知りたかないんだけどなぁ。今日中に読んで、さっさと返そ)
さっき、mixiのプロフィールを見たら、私の好きな本は、「吉行理恵 島尾ミホ ジュヌヴィエーヴ・ブリザック フラナリー・オコナー エミリー・ディキンスン 久生十蘭 深沢七郎」なんだって(なんだってって、自分が書いたプロフィールだろ?って感じだけど、何年も前に書いたんだもん)。
それ以外のものだってもちろん読んでいたけれど、まあ、そういう、偏りのある読書傾向だったのだ。
しかし、最近は、友人たちが私に、(有無をも言わさず)いろんな本を貸してくれる。直接手渡されることはもちろんだが、ウチの前を通りかかるたびに、お勧め本をポストに放り込んでいく人もいるし、宅急便で送ってくる人までいる。
おまけに。
本好きの長女が、これまたお勧めの本を「読め読め」と、迫ってくる。彼女が貸してくれる本は、彼女が図書館で借りてきた本なので、さっさと読んで返さなければならない。彼女は、自由に本を買えるほどお小遣いを与えられていないので、4枚の図書館カード(住んでいる区の図書館、学校のある区の図書館、学校の中等部の図書館と高等部の図書館)を駆使して、大量の本を借りてくるのだ。
そんなわけで。
私の机の上には、読まなければならない本が、山積みになっている。私は、自分の趣味とは全く異なる本を、苦行のように(?)せっせと読んでいる。つまんなくても、我慢して読んでいる。これで、私の世界は広がるんだろーか?
(商品レビューにあるのは、「中学生の気持ちが知りたかったら、コレ読んで!」と、さっき長女に押し付けられて、半分程、読んだ本。別に、中学生の気持ちなんか、知りたかないんだけどなぁ。今日中に読んで、さっさと返そ)
子どもの頃から、暮しの手帖を読んでいる。
母が1世紀の頃から買って大切に保存していたのを、1冊ずつ取り出しては、繰り返し読んだ。
知らないうちに、花森安治のセンスと思想に、とりこになっていた。
やがて花森安治は亡くなり、私は成長し、そして結婚して、母の元を離れた。それからは、自分で暮しの手帖を買っている。相当面白くなかった時期も、ほとんど意地で買い続けた。私が買わなければ、誰も買わないような気がして。
最近は編集長も変わり、一時期よりもややマシになったと思う。
さて、その暮しの手帖を、今度は私の長女が愛読している。
今朝、起きてみると、台所に、フレンチトーストが作ってあった。私と次女の分を作ったと書置きしてあった。(彼女は早い時間にピアノのレッスンに出かけたのだ)。傍らには暮しの手帖の最新号があった。レシピを見て作ったらしい。
とっても、美味しかった!
私は長年、この雑誌を愛読しているのに、レシピを見て料理を作ったことは一度もない。料理が好きでないのだ。食べることに興味がないのだ。そんな私に、この雑誌のレシピは、ややこしすぎる。
だから。
ブラボー!長女!なのである。これからも、暮しの手帖のレシピを見て、どんどん料理を作っておくれ!
本日。朝、長女はピアノ。たくさん宿題を出されたらしい。
私は、午前、太極拳。
お昼に私の母の家に集合して、手巻き寿司をご馳走になり、午後、私はお煎茶道の稽古に出かけた。
中身の濃いお稽古事日であった。
母が1世紀の頃から買って大切に保存していたのを、1冊ずつ取り出しては、繰り返し読んだ。
知らないうちに、花森安治のセンスと思想に、とりこになっていた。
やがて花森安治は亡くなり、私は成長し、そして結婚して、母の元を離れた。それからは、自分で暮しの手帖を買っている。相当面白くなかった時期も、ほとんど意地で買い続けた。私が買わなければ、誰も買わないような気がして。
最近は編集長も変わり、一時期よりもややマシになったと思う。
さて、その暮しの手帖を、今度は私の長女が愛読している。
今朝、起きてみると、台所に、フレンチトーストが作ってあった。私と次女の分を作ったと書置きしてあった。(彼女は早い時間にピアノのレッスンに出かけたのだ)。傍らには暮しの手帖の最新号があった。レシピを見て作ったらしい。
とっても、美味しかった!
私は長年、この雑誌を愛読しているのに、レシピを見て料理を作ったことは一度もない。料理が好きでないのだ。食べることに興味がないのだ。そんな私に、この雑誌のレシピは、ややこしすぎる。
だから。
ブラボー!長女!なのである。これからも、暮しの手帖のレシピを見て、どんどん料理を作っておくれ!
本日。朝、長女はピアノ。たくさん宿題を出されたらしい。
私は、午前、太極拳。
お昼に私の母の家に集合して、手巻き寿司をご馳走になり、午後、私はお煎茶道の稽古に出かけた。
中身の濃いお稽古事日であった。
長女の友達が、次女のために持ってきてくれた。
小峰書店 赤い鳥名作童話(1982年発行) を 6冊
上等な文章、美しい物語。装丁も素晴らしくて、うっとりする。
次女は、ひとつひとつを丁寧に読んで、感想を伝えてくれる。
それは、母親である私に、幸せをもたらす。
「あと、5冊あるの。こんど、持ってくるね」と、次女に約束していた、長女の友達。
ありがとね!
小峰書店 赤い鳥名作童話(1982年発行) を 6冊
上等な文章、美しい物語。装丁も素晴らしくて、うっとりする。
次女は、ひとつひとつを丁寧に読んで、感想を伝えてくれる。
それは、母親である私に、幸せをもたらす。
「あと、5冊あるの。こんど、持ってくるね」と、次女に約束していた、長女の友達。
ありがとね!
「チーム・バチスタの栄光」「ナイチンゲールの沈黙」「螺鈿迷宮」「ジェネラル・ルージュの凱旋」の4冊。
ウチに遊びに来た友人(内科医)が、置いてったのである。
「これ、おもしろいよ〜。リアリティあるの!読んで、読んで〜」と。
ちなみに彼女の旦那は、大学病院の准教授である。
手術室勤務の長かった、看護士の友人も言うのである。
「海堂尊の小説って、ホントに現場を知ってる医者じゃなきゃ書けないものだね」と。
ちなみに彼女の旦那は、麻酔科医である。
普段はエンタメ系小説は読まないのだが、そんなに医療関係者がオススメするならと、読んでやったぜ。
感想。
これが、ホントにリアルなら、あたしは、大学病院の、ひいては、日本の医療の、世話にはなりたくないね。
ウチに遊びに来た友人(内科医)が、置いてったのである。
「これ、おもしろいよ〜。リアリティあるの!読んで、読んで〜」と。
ちなみに彼女の旦那は、大学病院の准教授である。
手術室勤務の長かった、看護士の友人も言うのである。
「海堂尊の小説って、ホントに現場を知ってる医者じゃなきゃ書けないものだね」と。
ちなみに彼女の旦那は、麻酔科医である。
普段はエンタメ系小説は読まないのだが、そんなに医療関係者がオススメするならと、読んでやったぜ。
感想。
これが、ホントにリアルなら、あたしは、大学病院の、ひいては、日本の医療の、世話にはなりたくないね。
吉行理恵が好き。
言葉の紡ぎ方が好き。丁寧にそれは丁寧に推敲された、美しい文章。
対象物との距離のとり方が好き。曖昧さがない。そこにはきっちりとした「表現」がある。
作品のなかに足を踏み入れると、彼女の描く世界の、ただの傍観者はでいられなくなる恐ろしさがある。これを読書の醍醐味と、言うよ?
最後の沈黙の長い年月。
これは、本人の望むところだったのかどうかは、わからないのだが。
もしかしたら、苦しさに満ちていたのかもしれないのだが。
それにしても。
凛とした佇まいを、想像させてくれて、心が、しんとなる。
こんなに素晴らしい作家にもかかわらず。
掌から砂がこぼれるみたいに、作品が世の中から、消えて無くなってしまう。
本屋には、無神経な言葉の羅列ばかりが氾濫しているのにね。ものすごい不条理。
言葉の紡ぎ方が好き。丁寧にそれは丁寧に推敲された、美しい文章。
対象物との距離のとり方が好き。曖昧さがない。そこにはきっちりとした「表現」がある。
作品のなかに足を踏み入れると、彼女の描く世界の、ただの傍観者はでいられなくなる恐ろしさがある。これを読書の醍醐味と、言うよ?
最後の沈黙の長い年月。
これは、本人の望むところだったのかどうかは、わからないのだが。
もしかしたら、苦しさに満ちていたのかもしれないのだが。
それにしても。
凛とした佇まいを、想像させてくれて、心が、しんとなる。
こんなに素晴らしい作家にもかかわらず。
掌から砂がこぼれるみたいに、作品が世の中から、消えて無くなってしまう。
本屋には、無神経な言葉の羅列ばかりが氾濫しているのにね。ものすごい不条理。
日本論 佐高信 × 姜尚中
2008年3月24日 読書この二人の発言内容は、(私にとって)おおむね、正論に思えた。
姜尚中の発言は、エドワード・サイードに通じるなあと思って、調べてみたら、やっぱり影響うけまくりのよう御様子。でも、彼の置かれている状況が、サイードほど逼迫していないから、詰めが甘いのかも。
それにしてもこの人って、インテリの韓流スターだね。
日本名の永野鉄男で、ルックスがもっと悪かったら、こんなにブレイクしていたか?著作のうちの何冊かは、写真が表紙になってるし。自己プロデュースがうまいということか。タートルネックセーターがお似合いな、したたかなヤツである。
姜尚中の発言は、エドワード・サイードに通じるなあと思って、調べてみたら、やっぱり影響うけまくりのよう御様子。でも、彼の置かれている状況が、サイードほど逼迫していないから、詰めが甘いのかも。
それにしてもこの人って、インテリの韓流スターだね。
日本名の永野鉄男で、ルックスがもっと悪かったら、こんなにブレイクしていたか?著作のうちの何冊かは、写真が表紙になってるし。自己プロデュースがうまいということか。タートルネックセーターがお似合いな、したたかなヤツである。
1 2