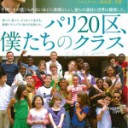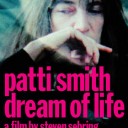パリ20区、僕たちのクラス
2010年8月1日 映画 コメント (2)
エネと岩波ホールへ。
この映画を、エネに見せたかったのである。
この映画に出てくる様々な人種の子供たちは、エネにとっては同胞だから。
自分と同じ世代のフランス人が、どのような学校生活を送っているか、知ってほしかった。
エネの感想は…
「フランスの学校って、教室が狭い。椅子も机も小さすぎる。体が大きいのに、あんな窮屈な所へ押し込められたんじゃ、イライラするのも無理はない。もっとゆとりのある空間なら、気持ちに余裕も生まれるんじゃないの?」
と、冷静なご意見。
確かに…。せまっ苦しいところで、激しい言葉の応酬をするから、熱くなりやすいのよね…。
「あたし、日本で暮らせててよかったよ。あんな学校でサバイバルできるって気がしないもん」
「でもさあ、あたしの中の、ああ言えばこう言う的なところは、フランス魂なのか!と、納得したよ」
自分の短所をフランス人気質で片づけるなよ!?
お昼は、すずらん通りのロシア料理店で。
古本屋インフォーメーションオフィスでくつろいだり、昭和ものを揃えている本屋さんであれこれ眺めたり、スポーツ用品店でカデットのためにゴーグルを買ったり、神保町を満喫した一日であった。
この映画を、エネに見せたかったのである。
この映画に出てくる様々な人種の子供たちは、エネにとっては同胞だから。
自分と同じ世代のフランス人が、どのような学校生活を送っているか、知ってほしかった。
エネの感想は…
「フランスの学校って、教室が狭い。椅子も机も小さすぎる。体が大きいのに、あんな窮屈な所へ押し込められたんじゃ、イライラするのも無理はない。もっとゆとりのある空間なら、気持ちに余裕も生まれるんじゃないの?」
と、冷静なご意見。
確かに…。せまっ苦しいところで、激しい言葉の応酬をするから、熱くなりやすいのよね…。
「あたし、日本で暮らせててよかったよ。あんな学校でサバイバルできるって気がしないもん」
「でもさあ、あたしの中の、ああ言えばこう言う的なところは、フランス魂なのか!と、納得したよ」
自分の短所をフランス人気質で片づけるなよ!?
お昼は、すずらん通りのロシア料理店で。
古本屋インフォーメーションオフィスでくつろいだり、昭和ものを揃えている本屋さんであれこれ眺めたり、スポーツ用品店でカデットのためにゴーグルを買ったり、神保町を満喫した一日であった。
猫が行方不明 HDニューマスター版 [DVD]
2010年7月8日 映画
を買った。
ミュージック・ギフト券がもうすぐタワレコで使えなくなるそうなんで、
家にあった券をかき集めて買いに行った。
だって、すごーーーーく、好きな映画なんだもん。
オープニングが、カッコよすぎる!
あのカッコよさは、フツーじゃない。
登場人物も、音楽も、映像も、編集も、全部好き。
ラストで主人公の女の子が、走るところ、背中がゾクゾクしちゃう。
あそこでPortisheadを使うなんて、反則だよと言いたくなるくらい、美しい場面だ。
ミュージック・ギフト券がもうすぐタワレコで使えなくなるそうなんで、
家にあった券をかき集めて買いに行った。
だって、すごーーーーく、好きな映画なんだもん。
オープニングが、カッコよすぎる!
あのカッコよさは、フツーじゃない。
登場人物も、音楽も、映像も、編集も、全部好き。
ラストで主人公の女の子が、走るところ、背中がゾクゾクしちゃう。
あそこでPortisheadを使うなんて、反則だよと言いたくなるくらい、美しい場面だ。
「9歳の女の子・ユキ(ノエ・サンピ)は、フランス人の父・フレデリック(イポリット・ジラルド)と日本人の母・ジュン(ツユ)とパリで暮らしている。ある日、母が父と別れてユキと日本で暮らしたいと考えていることを知り、ユキは大きなショックを受ける。親友のニナ(アリエル・ムーテル)とも離れたくないし、今の生活を変えたくない。ユキはニナと一緒に、両親の離婚を止めようと、愛し合っていた頃を思い出してもらえるように“愛の妖精”からと装って母に手紙を送るが、うまくいかない。最後の手段として家出を決意する二人。大急ぎで支度を整え、ユキとニナは嘘の書置きを残して出発する。静かな郊外。ニナが昔、父と行った小屋を探しているうちに、気がつくと二人は深い森の仲へと迷い込んでいた。「戻ったほうがいいかも」とニナはユキに声をかけるが、ユキはニナとは反対の方向へ進んでいく。険しい道をかき分けて森を抜けると、せみの鳴き声が遠くから聞こえてくる。すると突然、ユキの目の前に日本の田園風景が広がっていた。「こっちで一緒に遊ぼうよ」と日本の女の子たちに声をかけられ、ユキは古い日本家屋の畳の上でカルタや座布団取りをして、時間を忘れて遊ぶ。そのうち皆家に帰っていき、ユキも再び森へと走って戻っていく。ユキを探す父の声が聞こえてくる。大声で叫び、森の中で立ちすくむ父の姿を見つけたユキは、ゆっくりと近づいていった……。夏の終わり。ユキは母と日本で暮らし始めた。母が子供の頃に住んでいた場所での新しい生活。少し大人になったユキ、少し強くなった母、そしてフランスで暮らす父やニナ。みんながそれぞれに、新たな一歩を踏み出していく……。」
とゆう映画を、見てきたのである。エネとカデットと恵比寿ガーデンシネマにて。
新聞の映画評を読んで、「ウチの子たちのためにあるような映画」だと思った。
でも、私からこの映画を見に行くのを提案するのはよしていた。
彼女たちが自らこの映画を見つけ出して、「行きたい!」と言ったら、連れて行こうと思った。そしたら、案の定、
「お母さん、あたしたち、見たい映画があるんだけど!」と!
泣き虫のエネは、泣きっぱなし(←でも、この人、予告にあった、老人のラヴ・ストーリーで既に泣いていたからね…)
主人公のユキと同じ9歳で日仏ハーフという立場のカデットは、自分自身とあまりにもシンクロしていたためか、途中から私にすがりつくようにして、画面を見ていた。
まあ、ウチ的に悪い映画ではなかったし、ユキ役の女の子も非常に良かったのだけれど…
映画としての完成度は…残念ながら低い。
と、帰りがけに娘たちに言ったら、
「お母さん、何様!?」
と言われたが、私は、お金を払って映画を見る、観客様です。
お昼は、ガーデンプレイスの裏の小さなフレンチレストランで食べた。
安くて、美味しくて、サービスよくて、優秀なり。
とゆう映画を、見てきたのである。エネとカデットと恵比寿ガーデンシネマにて。
新聞の映画評を読んで、「ウチの子たちのためにあるような映画」だと思った。
でも、私からこの映画を見に行くのを提案するのはよしていた。
彼女たちが自らこの映画を見つけ出して、「行きたい!」と言ったら、連れて行こうと思った。そしたら、案の定、
「お母さん、あたしたち、見たい映画があるんだけど!」と!
泣き虫のエネは、泣きっぱなし(←でも、この人、予告にあった、老人のラヴ・ストーリーで既に泣いていたからね…)
主人公のユキと同じ9歳で日仏ハーフという立場のカデットは、自分自身とあまりにもシンクロしていたためか、途中から私にすがりつくようにして、画面を見ていた。
まあ、ウチ的に悪い映画ではなかったし、ユキ役の女の子も非常に良かったのだけれど…
映画としての完成度は…残念ながら低い。
と、帰りがけに娘たちに言ったら、
「お母さん、何様!?」
と言われたが、私は、お金を払って映画を見る、観客様です。
お昼は、ガーデンプレイスの裏の小さなフレンチレストランで食べた。
安くて、美味しくて、サービスよくて、優秀なり。
マリー・アントワネット
2009年12月12日 映画
長女と次女と3人で鑑賞。
(夫が外出中に! だって、一緒に見てたら、時代考証がどーのこーのと、文句言うに決まってるモン!)
ファッションやお菓子が、カラフルでポップ。
音楽がUKロックでイカシテイル。
ってことで、いまどきの女の子的には、まー楽しめる。
(フランスの歴史のホントに常識的なことを知っていればね!
そんなこと何も知らない次女は、
「ねー、どうして、オーストリアのひとがフランスのお姫様になるの?」
とか、いちいち質問を浴びせかけるので辟易した…)
映画的には、低レベル。
ここまでやるんなら、もっとラジカルに、疾走感あふれる作品にすればよいのにと思う。
それは、ソフィア・コッポラの作品を見るたびにいつも感じること。
この人の中途半端さが好きじゃないの。
長女は見終わって、
「今すぐに、もう一回見たい!!」
と、言った。もちろん、見せなかったけど。
(夫が外出中に! だって、一緒に見てたら、時代考証がどーのこーのと、文句言うに決まってるモン!)
ファッションやお菓子が、カラフルでポップ。
音楽がUKロックでイカシテイル。
ってことで、いまどきの女の子的には、まー楽しめる。
(フランスの歴史のホントに常識的なことを知っていればね!
そんなこと何も知らない次女は、
「ねー、どうして、オーストリアのひとがフランスのお姫様になるの?」
とか、いちいち質問を浴びせかけるので辟易した…)
映画的には、低レベル。
ここまでやるんなら、もっとラジカルに、疾走感あふれる作品にすればよいのにと思う。
それは、ソフィア・コッポラの作品を見るたびにいつも感じること。
この人の中途半端さが好きじゃないの。
長女は見終わって、
「今すぐに、もう一回見たい!!」
と、言った。もちろん、見せなかったけど。
柄本明主演 4連発!
2009年12月8日 映画
見るときゃ、見る!のである。
・ カンゾー先生
柄本明の使い方が良いですなあ。作品としての完成度も高いし。まー、今村昌平だもんね。
・ やじきた道中 てれすこ
柄本明本人としては、本領発揮といった感じ。勘三郎と仕事するのが楽しくて仕方ない様子。
・ センセイの鞄
柄本明の存在の奇天烈さを、久世光彦が存分に利用した作品。小泉今日子が、「せんせぇ!」と甘えた声を発するたびに、寒気を覚えた。
・ ぶるうかなりや
キャストは素晴らしいのに、どうしてこんなつまらない作品になったのか? ナゾー!
なんだかんだいっても、大好きな人を一気に堪能できたから、幸せでごじゃりました。
・ カンゾー先生
柄本明の使い方が良いですなあ。作品としての完成度も高いし。まー、今村昌平だもんね。
・ やじきた道中 てれすこ
柄本明本人としては、本領発揮といった感じ。勘三郎と仕事するのが楽しくて仕方ない様子。
・ センセイの鞄
柄本明の存在の奇天烈さを、久世光彦が存分に利用した作品。小泉今日子が、「せんせぇ!」と甘えた声を発するたびに、寒気を覚えた。
・ ぶるうかなりや
キャストは素晴らしいのに、どうしてこんなつまらない作品になったのか? ナゾー!
なんだかんだいっても、大好きな人を一気に堪能できたから、幸せでごじゃりました。
岩波ホールにて。
「あたしが見なくて、誰が見るんだ!?」ってゆうくらい、アニエス・ヴァルダが好き。
この映画も、まことに、まことに、素晴らしかった。
アニエス・ヴァルダって、奇跡の人だわーと。
神に選ばれた人なんだわーと。思った。
彼女の才能に満ち満ちた過去と現在の、とてつもなくスタイリッシュなコラージュ。
彼女は聡明で、エネルギッシュ、アイデアにあふれ、センスがずば抜けている。
そして、なによりも、出会った人々に暖かい愛を降り注ぐ。
以前、フランスのテレビで見た、「タゲール街の人々」(1975)(←名作!)の撮影秘話があったのが、ちょー嬉しかった!
「あたしが見なくて、誰が見るんだ!?」ってゆうくらい、アニエス・ヴァルダが好き。
この映画も、まことに、まことに、素晴らしかった。
アニエス・ヴァルダって、奇跡の人だわーと。
神に選ばれた人なんだわーと。思った。
彼女の才能に満ち満ちた過去と現在の、とてつもなくスタイリッシュなコラージュ。
彼女は聡明で、エネルギッシュ、アイデアにあふれ、センスがずば抜けている。
そして、なによりも、出会った人々に暖かい愛を降り注ぐ。
以前、フランスのテレビで見た、「タゲール街の人々」(1975)(←名作!)の撮影秘話があったのが、ちょー嬉しかった!
公開当時、ニースの映画館で、私はひとりでこの映画を見た。
長女が7歳のとき、ビデオ屋で借り、夫と長女と3人で見た。
長女は座布団を抱いて、最初から最後まで泣きっぱなしだった。
夫も涙を流しっぱなしだった。
数日前、アマゾンで中古のDVDが廉価で売られているのを見つけて、注文したのが届き、今回は次女を含めた4人で見た。
長女は、画面から少し離れたピアノの椅子に座って、始終すすり泣いていた。
見終わると、「泣きすぎて頭が痛い」とのたもうた。
次女は、ずっと私にくっつき、ポネットが泣くときは自分も泣き、
「こんなに悲しくさせる映画は、いじめだ」と、恨んだ。
夫は、泣きたくなると、トイレに行ったり、台所に立ったりしていた模様である。
これは、我が家の「号泣映画」に認定してもよかろう!
私は一度も泣いてないけど!
(私がこの映画が好きな理由は、子供の身に付けている服や、靴や、リュックサックが可愛いからである!)
死んだ母親役のマリー・トランティニャンは、2003年に、リトアニアで恋人に殴られて、本当に亡くなった。この役を演じたとき、自分がそんな死に方をするとは、夢にも思わなかったことだろう。
事実は、小説より、映画より、奇なり。
長女が7歳のとき、ビデオ屋で借り、夫と長女と3人で見た。
長女は座布団を抱いて、最初から最後まで泣きっぱなしだった。
夫も涙を流しっぱなしだった。
数日前、アマゾンで中古のDVDが廉価で売られているのを見つけて、注文したのが届き、今回は次女を含めた4人で見た。
長女は、画面から少し離れたピアノの椅子に座って、始終すすり泣いていた。
見終わると、「泣きすぎて頭が痛い」とのたもうた。
次女は、ずっと私にくっつき、ポネットが泣くときは自分も泣き、
「こんなに悲しくさせる映画は、いじめだ」と、恨んだ。
夫は、泣きたくなると、トイレに行ったり、台所に立ったりしていた模様である。
これは、我が家の「号泣映画」に認定してもよかろう!
私は一度も泣いてないけど!
(私がこの映画が好きな理由は、子供の身に付けている服や、靴や、リュックサックが可愛いからである!)
死んだ母親役のマリー・トランティニャンは、2003年に、リトアニアで恋人に殴られて、本当に亡くなった。この役を演じたとき、自分がそんな死に方をするとは、夢にも思わなかったことだろう。
事実は、小説より、映画より、奇なり。
昨日の夜でタミフルを飲み切り、本日より長女は健康人であると、我が家では認定されたなり!
彼女の掛け布団を干し、布団カバーと枕カバーとシーツとベッドパッドを洗濯した。
5日間寝たきりだったので、リハビリとして散歩がてら、次女と夫とともに、少し遠いU通りのサンドイッチ屋さんまでお昼を買いに行かせた。ここのサンドイッチは豪華で、美味しい!高いけど!
午後は、次女と長女とDVDで映画鑑賞。
la vie en roseさんがコメントに記してくださった『エル・スール』。
子供時代のエストレリャと、思春期のエストレリャが、ちょうど次女と長女の年齢に重なる。
右に小さなエストレリャ、左に大きなエストレリャを従え、母親冥利に尽きるひとときであった。
鑑賞後、お互い特に感想は言わなかったけれど、二人ともそれぞれに、感じ入っている様子だった。
彼女の掛け布団を干し、布団カバーと枕カバーとシーツとベッドパッドを洗濯した。
5日間寝たきりだったので、リハビリとして散歩がてら、次女と夫とともに、少し遠いU通りのサンドイッチ屋さんまでお昼を買いに行かせた。ここのサンドイッチは豪華で、美味しい!高いけど!
午後は、次女と長女とDVDで映画鑑賞。
la vie en roseさんがコメントに記してくださった『エル・スール』。
子供時代のエストレリャと、思春期のエストレリャが、ちょうど次女と長女の年齢に重なる。
右に小さなエストレリャ、左に大きなエストレリャを従え、母親冥利に尽きるひとときであった。
鑑賞後、お互い特に感想は言わなかったけれど、二人ともそれぞれに、感じ入っている様子だった。
パティ・スミス:ドリーム・オブ・ライフ
2009年9月17日 映画
パティ・スミスのライヴに、何回か行ったことがある。
華奢で繊細で詩的な外観とは裏腹に、
熱いロックのライヴだった。ちょっと、ダサいかも?ってくらい。
以前に行った、彼女の詩と写真の展覧会では、
ヨーロッパの芸術家の模倣が数多く見受けられたが、
それに関してのためらいが、全く彼女にはないので、かえってすがすがしかった。
この映画の、儚げで美しい映像の中でも彼女は、
実にタフで、エネルギッシュ。歌声はもちろんパワフル。
親しい人たちの死の悲しみも、エネルギーに変換していた。
とはいえ彼女は、いつでもぎこちなく、不器用だ。
舞台の上で叫ぶときも、アルチュール・ランボーの墓参りに行くときも、ポラロイドを剥がすときも、子供の赤ちゃんの頃の服を取り出すときも。
クラリネットは、わたしより下手だと確信した(!?)
でも、そこがいんだなー。きっと。わたしとしては。
編み上げのワークブーツは、相変わらず健在。素晴らしい!
この映画、本当は友人Sと一緒に行くはずだったんだけど、
彼女の、7月に手術をしたお父さんが検査入院したため、ひとりで見に行った。
華奢で繊細で詩的な外観とは裏腹に、
熱いロックのライヴだった。ちょっと、ダサいかも?ってくらい。
以前に行った、彼女の詩と写真の展覧会では、
ヨーロッパの芸術家の模倣が数多く見受けられたが、
それに関してのためらいが、全く彼女にはないので、かえってすがすがしかった。
この映画の、儚げで美しい映像の中でも彼女は、
実にタフで、エネルギッシュ。歌声はもちろんパワフル。
親しい人たちの死の悲しみも、エネルギーに変換していた。
とはいえ彼女は、いつでもぎこちなく、不器用だ。
舞台の上で叫ぶときも、アルチュール・ランボーの墓参りに行くときも、ポラロイドを剥がすときも、子供の赤ちゃんの頃の服を取り出すときも。
クラリネットは、わたしより下手だと確信した(!?)
でも、そこがいんだなー。きっと。わたしとしては。
編み上げのワークブーツは、相変わらず健在。素晴らしい!
この映画、本当は友人Sと一緒に行くはずだったんだけど、
彼女の、7月に手術をしたお父さんが検査入院したため、ひとりで見に行った。
封印は破られるためにあるのだからして。
購入したけど、当分は見ないでおこうと思っていたDVDボックスを、あっさりと紐解いた。
自宅軟禁・一人勉強合宿中の長女と一緒に、その特典映像まできっちりと見た。
ハリポタ映画なんぞを喜んで見に行く、大衆映画的感性しかない長女についてこれるか?と思ったが、アナ・トレントの可愛さ故か、熱心に鑑賞していた。
途中で、ハチミツを舐めながら、長女の入れてくれた紅茶を飲んだ。
このDVDの映像はは、私の記憶にある、映画館で見たときのそれに比べて、非常に明るく、陰影に乏しい。
でも、エリセ自身が監修したそーなのだから、これでいんだろう。
購入したけど、当分は見ないでおこうと思っていたDVDボックスを、あっさりと紐解いた。
自宅軟禁・一人勉強合宿中の長女と一緒に、その特典映像まできっちりと見た。
ハリポタ映画なんぞを喜んで見に行く、大衆映画的感性しかない長女についてこれるか?と思ったが、アナ・トレントの可愛さ故か、熱心に鑑賞していた。
途中で、ハチミツを舐めながら、長女の入れてくれた紅茶を飲んだ。
このDVDの映像はは、私の記憶にある、映画館で見たときのそれに比べて、非常に明るく、陰影に乏しい。
でも、エリセ自身が監修したそーなのだから、これでいんだろう。
忌野清志郎 完全復活祭 日本武道館 [DVD]
2009年7月5日 映画
清志郎は、これをやるために、完全復活したのだ。
愛と平和を、ロックを通して、訴えるために。
そして、存分にシャウトして、さっと天国に行った。
イエス・キリストの復活みたい。
見てる間中、心の中はどしゃ降り。
だけど、ベイベー、あなたに会えてよかった。
ギターの三宅伸治、かっこいいなあ。
ちょっと、好きになった。
昼間は、次女のゴスペル・ワークショップの発表会を見に行った。
愛と平和を、ロックを通して、訴えるために。
そして、存分にシャウトして、さっと天国に行った。
イエス・キリストの復活みたい。
見てる間中、心の中はどしゃ降り。
だけど、ベイベー、あなたに会えてよかった。
ギターの三宅伸治、かっこいいなあ。
ちょっと、好きになった。
昼間は、次女のゴスペル・ワークショップの発表会を見に行った。
ビクトル・エリセ DVD-BOX
2009年6月23日 映画 コメント (2)
初めて自分のために、DVDを買った。
映画は、映画館で見るのが大前提。
そうでなければ、借りて、見て、返すもの。
自分で所有するなんておこがましいと思っていた。
『ミツバチのささやき』も『エル・スール』も、何度も映画館に足を運んだ。
テレビで放映されたときは録画したけれど、そのビデオを再生したことは一度もない。
でも、でも、でも。
どうしても、このDVDだけは、自分のものにしたくて、買ってしまった。
畏るべし、アマゾンのワンクリック!
今日の午後に届いたこのボックスは、文学全集のように美しい。
私は、当分、このDVDを見ることはないだろう。
「持っている」という行為を、自分の中で消化しなくては、まず。
ああ、でも、「持っていれば」、人に貸すことができる。
今度Nに貸すかもしれない。
きっと彼女も好きになるはずだから、。
でもさ、これ買ったら、キェシロフスキも欲しくなってしまって。
『ふたりのベロニカ』だけでいいんだけど。
年取って、欲張りになったあたし。
もしくは、アマゾンの餌食になっているあたし。
映画は、映画館で見るのが大前提。
そうでなければ、借りて、見て、返すもの。
自分で所有するなんておこがましいと思っていた。
『ミツバチのささやき』も『エル・スール』も、何度も映画館に足を運んだ。
テレビで放映されたときは録画したけれど、そのビデオを再生したことは一度もない。
でも、でも、でも。
どうしても、このDVDだけは、自分のものにしたくて、買ってしまった。
畏るべし、アマゾンのワンクリック!
今日の午後に届いたこのボックスは、文学全集のように美しい。
私は、当分、このDVDを見ることはないだろう。
「持っている」という行為を、自分の中で消化しなくては、まず。
ああ、でも、「持っていれば」、人に貸すことができる。
今度Nに貸すかもしれない。
きっと彼女も好きになるはずだから、。
でもさ、これ買ったら、キェシロフスキも欲しくなってしまって。
『ふたりのベロニカ』だけでいいんだけど。
年取って、欲張りになったあたし。
もしくは、アマゾンの餌食になっているあたし。
カンヌで電力会社のストライキ
2009年5月29日 映画
菊地凛子主演のスペイン映画がコンペティション部門に出品されたけれど、無冠に終わり、日本的にはいまいち盛り上がらなかった今年の映画祭だが、実は、映画祭開催中に、ちょっとしたトラブルがあった。
それは…
電力会社がストライキを決行したこと!
「映画祭開催中のカンヌで19日(火)、フランスの電力会社EDFのストライキにより、電力供給がストップ。ジム・キャリーが登壇した“I Love You Phillip Morris”の上映会も途中で中断するというアクシデントに見舞われた。
午後3時よりストライキが始まると、カンヌの商店やホテル、住宅などで停電が開始。映画祭の本会場であるパレや映画館、一部のホテルは自家発電に切り替えており、映画祭をスケジュール通りに運営しているが、見本市の試写や商談には影響が及んでいるもようだ。
今年で62回目を迎える同映画祭は、世界中のメディアが注目するイベントだけに、これまでにも期間中に航空会社やタクシー会社によるストライキが決行されたことがある。EDFでは不況による経費削減のため、解雇や減給が計画されており、組合が抗議のためにストライキを起こしたと見られている。」
フランス人のストライキ魂は、筋金入り。
外野の私は、「やってくれるなぁ」と感心する。
そして。
受賞作品は、どれも、私の納得のいくものばかり。特に、シャルロット・ゲーンズブールが主演女優賞をとってブーイングの嵐だったというラース・フォン・トリアーの作品は、ぜひとも見たい!
審査委員長がイザベル・ユペールで、パルム・ドールが、彼女の主演作「ピアニスト」を2001年に撮ったミヒャエル・ハネケの作品だったということも、興味深い。公平性が高い証拠だと思う。
それは…
電力会社がストライキを決行したこと!
「映画祭開催中のカンヌで19日(火)、フランスの電力会社EDFのストライキにより、電力供給がストップ。ジム・キャリーが登壇した“I Love You Phillip Morris”の上映会も途中で中断するというアクシデントに見舞われた。
午後3時よりストライキが始まると、カンヌの商店やホテル、住宅などで停電が開始。映画祭の本会場であるパレや映画館、一部のホテルは自家発電に切り替えており、映画祭をスケジュール通りに運営しているが、見本市の試写や商談には影響が及んでいるもようだ。
今年で62回目を迎える同映画祭は、世界中のメディアが注目するイベントだけに、これまでにも期間中に航空会社やタクシー会社によるストライキが決行されたことがある。EDFでは不況による経費削減のため、解雇や減給が計画されており、組合が抗議のためにストライキを起こしたと見られている。」
フランス人のストライキ魂は、筋金入り。
外野の私は、「やってくれるなぁ」と感心する。
そして。
受賞作品は、どれも、私の納得のいくものばかり。特に、シャルロット・ゲーンズブールが主演女優賞をとってブーイングの嵐だったというラース・フォン・トリアーの作品は、ぜひとも見たい!
審査委員長がイザベル・ユペールで、パルム・ドールが、彼女の主演作「ピアニスト」を2001年に撮ったミヒャエル・ハネケの作品だったということも、興味深い。公平性が高い証拠だと思う。
「彼女の名はサビーヌ」
2009年2月27日 映画
という映画を、馬鹿寒い中、見に行った、友人Sと。
去年の末ごろから、一緒にこの映画を見に行くことを私たちは楽しみにしていて、今日が唯一、二人の都合のつく日だった。
フランスの女優サンドリーヌ・ボネールが、自閉症の妹サビーヌを撮ったドキュメンタリー。
繊細な感性を備えた、若い頃の美しいサビーヌ。
5年間の入院生活(拘束と大量の薬物療法)を経て、30キロ太り、よだれをたらすサビーヌ。
二つの時間を効果的に組み合わせたこの作品は、自閉症治療の問題を浮き彫りにする。
(ボネールは、インタビューで「監禁前と監禁後」と表現している)
ボネールの、カメラを通して妹を見つめる視線は、冷静で何事も見逃さず、そして暖かい。他の自閉症者やその家族に向ける眼差しにも愛情がこもっている。
彼女は、自分の知名度を利用して、妹にふさわしいアットホームな小規模の施設を作った(彼女自身がそう公言している)。しかし、誰がそれを責められよう? 彼女が主張するように、精神病患者のケアは国が引き受けるべきなのに、そうなっていない現状があるのだ。
そして、
「女優である自分が妹についての作品を作ることは“セレブ的行為”の一つとして受け取られてしまうのではないか、露骨で慎みがないことだと思われるのではないか」
という懸念を抱いたと言うが、そんな心配は無用だったと、私は思う。
なぜなら、芸術的な完成度の高い、優れた映画となったから。
バッハのプレリュードを弾く、現在のサビーヌと少女の頃のサビーヌの映像と音が重なったとき、彼女が本来持つ魂の崇高さに胸を突かれた。
(監禁後も、サビーヌはピアノを弾くことだけは忘れていなかったのだ)
見終わった後、Sと韓国料理を食べ、その後カフェへ移動して、沢山しゃべった。
Sは知的に障害を持った人たちの作業所で働いているので、彼女の映画の感想には、非常に重みがあった。
去年の末ごろから、一緒にこの映画を見に行くことを私たちは楽しみにしていて、今日が唯一、二人の都合のつく日だった。
フランスの女優サンドリーヌ・ボネールが、自閉症の妹サビーヌを撮ったドキュメンタリー。
繊細な感性を備えた、若い頃の美しいサビーヌ。
5年間の入院生活(拘束と大量の薬物療法)を経て、30キロ太り、よだれをたらすサビーヌ。
二つの時間を効果的に組み合わせたこの作品は、自閉症治療の問題を浮き彫りにする。
(ボネールは、インタビューで「監禁前と監禁後」と表現している)
ボネールの、カメラを通して妹を見つめる視線は、冷静で何事も見逃さず、そして暖かい。他の自閉症者やその家族に向ける眼差しにも愛情がこもっている。
彼女は、自分の知名度を利用して、妹にふさわしいアットホームな小規模の施設を作った(彼女自身がそう公言している)。しかし、誰がそれを責められよう? 彼女が主張するように、精神病患者のケアは国が引き受けるべきなのに、そうなっていない現状があるのだ。
そして、
「女優である自分が妹についての作品を作ることは“セレブ的行為”の一つとして受け取られてしまうのではないか、露骨で慎みがないことだと思われるのではないか」
という懸念を抱いたと言うが、そんな心配は無用だったと、私は思う。
なぜなら、芸術的な完成度の高い、優れた映画となったから。
バッハのプレリュードを弾く、現在のサビーヌと少女の頃のサビーヌの映像と音が重なったとき、彼女が本来持つ魂の崇高さに胸を突かれた。
(監禁後も、サビーヌはピアノを弾くことだけは忘れていなかったのだ)
見終わった後、Sと韓国料理を食べ、その後カフェへ移動して、沢山しゃべった。
Sは知的に障害を持った人たちの作業所で働いているので、彼女の映画の感想には、非常に重みがあった。
さっそく見に行った!
パンク好き、クドカン好きの私だもの、見に行かないわけないよ?
友人Mと友人Eと!
大いに笑って、沢山はしゃいだ。
宮崎あおいって、初めてしみじみ見たけれど、瞬発力がよくって、いい感じ!
Eが、
「篤姫やりながら、よくこの役できたね~。篤姫からこっちは簡単かもしれないけど、こっちから篤姫はキツイよ~」
と、しきりに感心していた。
(私は篤姫見ていない。Mのうちにはそもそもテレビがない…)
わたし的に言えば、佐藤浩市の病床のお父さん役は、三国連太郎で、中指立てたファックポーズでバッタリいって欲しかったわ。
わたしたちが気に入ったフレーズ、
「中年の好奇心をなめんじゃねーよ!」
あらゆる場面で使えそうです。
クドカンの趣味丸出し、やりたい放題の映画。そこがわたしには嬉しいんだけど、万人は理解してもらえないだろう。
でも、今までイイ仕事してきて(「流星の絆」もヒットしたし!)、だからこそのやりたい放題なんだから、これでいいのだ~
広くて居心地のいい映画館はガラガラだった。
内科医のMに母のことを話したら、症状と今までの治療をメモして、
「腕のいい神経内科の先生を知っているから、相談してみる」
と、言ってくれた。ありがと。
学校の行事で郊外に出かけていた長女が、帰りに母の見舞いに行ってくれた。
パンク好き、クドカン好きの私だもの、見に行かないわけないよ?
友人Mと友人Eと!
大いに笑って、沢山はしゃいだ。
宮崎あおいって、初めてしみじみ見たけれど、瞬発力がよくって、いい感じ!
Eが、
「篤姫やりながら、よくこの役できたね~。篤姫からこっちは簡単かもしれないけど、こっちから篤姫はキツイよ~」
と、しきりに感心していた。
(私は篤姫見ていない。Mのうちにはそもそもテレビがない…)
わたし的に言えば、佐藤浩市の病床のお父さん役は、三国連太郎で、中指立てたファックポーズでバッタリいって欲しかったわ。
わたしたちが気に入ったフレーズ、
「中年の好奇心をなめんじゃねーよ!」
あらゆる場面で使えそうです。
クドカンの趣味丸出し、やりたい放題の映画。そこがわたしには嬉しいんだけど、万人は理解してもらえないだろう。
でも、今までイイ仕事してきて(「流星の絆」もヒットしたし!)、だからこそのやりたい放題なんだから、これでいいのだ~
広くて居心地のいい映画館はガラガラだった。
内科医のMに母のことを話したら、症状と今までの治療をメモして、
「腕のいい神経内科の先生を知っているから、相談してみる」
と、言ってくれた。ありがと。
学校の行事で郊外に出かけていた長女が、帰りに母の見舞いに行ってくれた。
それでも生きる子供たちへ
2008年10月5日 映画
邦題が良くない!
原題は、「ALL THE INVISIBLE CHILDREN」だよ?
この邦題だと、まるで、「死」を前提にして生きている子供たちの映画みたいじゃないか!
「死」に抗って、「生」にしがみついているみたいじゃないか!
ここに登場する子供たちに、失礼なタイトルの付け方だ。
さて、映画自身についてであるが。
スバイク・リーのが、個人的には一番好きなテイストだった。
ジョン・ウーは、わざとらしすぎて、いただけない。
リドリー・スコットは、相変わらす霧が好きだなあと。
エミール・クストリッツァは、当然のことながら、リズムが冴えていて、子供がどうとか言うより、作品まるごと楽しめる。
いずれにしても。
子供の世界は、大人の世界の縮図なのである。
大人の世界の経済格差が、子供の貧富の格差に、一直線に通じる。
大人の不健康が、子供の健康を蝕む。
大人の悪意が、子供の心に乗り移る。
大人の戦争が、子供を戦士へと駆り立てる。
だから、子供がどうこうというよりも、大人が今の世界をきちんと整備しなけりゃならないのよね?
それを、世界中の大人に気付かせるためにこの映画は、イタリア外務省、、ユニセフ、WFP 国際連合世界食糧計画を巻き込んで作られたのだから、こんなヘンな邦題をつける日本の配給会社は大馬鹿だ!!!
原題は、「ALL THE INVISIBLE CHILDREN」だよ?
この邦題だと、まるで、「死」を前提にして生きている子供たちの映画みたいじゃないか!
「死」に抗って、「生」にしがみついているみたいじゃないか!
ここに登場する子供たちに、失礼なタイトルの付け方だ。
さて、映画自身についてであるが。
スバイク・リーのが、個人的には一番好きなテイストだった。
ジョン・ウーは、わざとらしすぎて、いただけない。
リドリー・スコットは、相変わらす霧が好きだなあと。
エミール・クストリッツァは、当然のことながら、リズムが冴えていて、子供がどうとか言うより、作品まるごと楽しめる。
いずれにしても。
子供の世界は、大人の世界の縮図なのである。
大人の世界の経済格差が、子供の貧富の格差に、一直線に通じる。
大人の不健康が、子供の健康を蝕む。
大人の悪意が、子供の心に乗り移る。
大人の戦争が、子供を戦士へと駆り立てる。
だから、子供がどうこうというよりも、大人が今の世界をきちんと整備しなけりゃならないのよね?
それを、世界中の大人に気付かせるためにこの映画は、イタリア外務省、、ユニセフ、WFP 国際連合世界食糧計画を巻き込んで作られたのだから、こんなヘンな邦題をつける日本の配給会社は大馬鹿だ!!!
去年の夏、友人C(既婚者)が、見に行ったと言っていたのだ。
「あたしのツバメと」。
自分よりずっと若い大学生のボーイフレンド(だか、恋人だか知らないけど)を、「ツバメ」と呼ぶ、その日本語のセンスにギョッとしたのだが、彼女の「ツバメ」話は、四季を超えて未だに続き(ツバメって渡り鳥じゃないの?という私の突っ込みは却下された)、「別れたい」と言ってたと思ったら、「向こうから別れ話を切り出されて、キレた」とか、すったもんだと忙しい。
さてさて、そんな二人が見に行った「バベル」だが。
Cに「どーだった?その映画」と、尋ねたけれども、「あーよかったよ」の反応くらいしかなくって、要領を得なくって(まあ、「ツバメ」と一緒じゃね)。
今回、DVDを借りてきて見て、要領を得ました、隅から隅まで。
こういう群像劇は、私の好むところなので、べたべた貼られている付箋が最初からよく見えて、予想通りの展開になってゆくところが、快感だあ。
登場人物にいちいち感情移入できる心地よさもある。
だけど。
要するに、(広い意味での)グローバリゼーションの付けは、最終的に弱者に回ってくるっていうオチ(モロッコの兄弟の兄と、メキシコ人のベビーシッター)が、どうにも単純すぎて、解せない。
菊地凛子は逸材だが、日本で彼女を上手に使いこなせる監督はいないだろう。
この話、Cにしたいんけど、映画の内容なんか、とっくに忘れてるだろうなあ。
「あたしのツバメと」。
自分よりずっと若い大学生のボーイフレンド(だか、恋人だか知らないけど)を、「ツバメ」と呼ぶ、その日本語のセンスにギョッとしたのだが、彼女の「ツバメ」話は、四季を超えて未だに続き(ツバメって渡り鳥じゃないの?という私の突っ込みは却下された)、「別れたい」と言ってたと思ったら、「向こうから別れ話を切り出されて、キレた」とか、すったもんだと忙しい。
さてさて、そんな二人が見に行った「バベル」だが。
Cに「どーだった?その映画」と、尋ねたけれども、「あーよかったよ」の反応くらいしかなくって、要領を得なくって(まあ、「ツバメ」と一緒じゃね)。
今回、DVDを借りてきて見て、要領を得ました、隅から隅まで。
こういう群像劇は、私の好むところなので、べたべた貼られている付箋が最初からよく見えて、予想通りの展開になってゆくところが、快感だあ。
登場人物にいちいち感情移入できる心地よさもある。
だけど。
要するに、(広い意味での)グローバリゼーションの付けは、最終的に弱者に回ってくるっていうオチ(モロッコの兄弟の兄と、メキシコ人のベビーシッター)が、どうにも単純すぎて、解せない。
菊地凛子は逸材だが、日本で彼女を上手に使いこなせる監督はいないだろう。
この話、Cにしたいんけど、映画の内容なんか、とっくに忘れてるだろうなあ。
コメントをみる | 

絶望的なまでに救いようのない男の話である。
しかし妙な感情移入をするこはとなく、ときには滑稽さのあまり、これが悲劇であることを忘れて、苦笑した。
それは、アキ・カウリスマキの徹底的な美学に基づいた映像の中で起きている物語だということを、観客(私)は、知っているからだ。
登場人物はおしなべて仏頂面。舞台は、使い古されて、昔の匂いがぷんぷんするような場所ばかり。
主人公コイスティネンの、人間としての自然なしぐさを垣間見るのは、二つのシーンだけ。刑務所の中で無邪気に笑っている瞬間と、ソーセージ売りの女性に手を重ねる、最後の場面。
カウリスマキって、フィンランドを代表する映像作家だけど、彼の映画には、一般的にフィンランドという国から連想されるようなものは、何一つ登場しない。(高い教育水準とか?おしゃれな北欧家具とか?カラフルな街並みとか?素朴な自然とか?)そこに、すごく好感が持てるなあ。
逆に、カウリスマキの映画でフィンランドに憧れて行った人は、ずいぶんがっかりすることだろうけどね。
しかし妙な感情移入をするこはとなく、ときには滑稽さのあまり、これが悲劇であることを忘れて、苦笑した。
それは、アキ・カウリスマキの徹底的な美学に基づいた映像の中で起きている物語だということを、観客(私)は、知っているからだ。
登場人物はおしなべて仏頂面。舞台は、使い古されて、昔の匂いがぷんぷんするような場所ばかり。
主人公コイスティネンの、人間としての自然なしぐさを垣間見るのは、二つのシーンだけ。刑務所の中で無邪気に笑っている瞬間と、ソーセージ売りの女性に手を重ねる、最後の場面。
カウリスマキって、フィンランドを代表する映像作家だけど、彼の映画には、一般的にフィンランドという国から連想されるようなものは、何一つ登場しない。(高い教育水準とか?おしゃれな北欧家具とか?カラフルな街並みとか?素朴な自然とか?)そこに、すごく好感が持てるなあ。
逆に、カウリスマキの映画でフィンランドに憧れて行った人は、ずいぶんがっかりすることだろうけどね。
コメントをみる | 

ボブ・ディラン ノー・ディレクション・ホーム
2008年10月2日 映画
この映画を一番楽しんだのは、監督のマーティン・スコセッシであろう。
1942年生まれの彼は、同年代の若いボブ・ディラン(1941年生まれ)が活躍し、人々の注目を集めるのを、憧れと嫉妬が混じった気持ちで見ていたに違いない。
だから60年代のディランに興味深々で、あの時に知りたかったことを、40年経ってから、周辺の人々に根掘り葉掘り聞き、お宝映像をかき集めた。そして自らは有名映画監督として、正々堂々とディランにインタビューすることができた。
よかったねえ。
それにしても。
アコギをエレキに持ち変えただけで、ものすごいバッシングに合うなんて、異常な事態だ。当時の人々は、楽器に主義・主張が宿っていると考えていたのだろうか?人間の思い込みって、恐ろしい。
しかしながら。
そんなことも含めて、ボブ・ディランは、時代に迎合するのではなくて、時代を自分に迎合させる才能を持っていた。
それでもって。
若いときのディランって、ホントによいのよね、音楽もだけど、ルックスが。伏目がちでナイーブなあの表情、もしも私が当時のアメリカ人女子だったら、絶対にミーハー的なファンになっていたよ!
とはいえ。
ディランの音楽を、現在の私は時おーり好んで聞くが、これはきっと、英語だからいいんだと思う。もしも日本語で同じ内容を歌われたら、鬱陶しくてかなわないような気がする。
しかし、208分は、ちと長いね。
ムスメたちに、「お母さん、また、その映画見てるの?」と、言われ続けた。
「また」じゃなくて、「まだ」だったんだよ。
1942年生まれの彼は、同年代の若いボブ・ディラン(1941年生まれ)が活躍し、人々の注目を集めるのを、憧れと嫉妬が混じった気持ちで見ていたに違いない。
だから60年代のディランに興味深々で、あの時に知りたかったことを、40年経ってから、周辺の人々に根掘り葉掘り聞き、お宝映像をかき集めた。そして自らは有名映画監督として、正々堂々とディランにインタビューすることができた。
よかったねえ。
それにしても。
アコギをエレキに持ち変えただけで、ものすごいバッシングに合うなんて、異常な事態だ。当時の人々は、楽器に主義・主張が宿っていると考えていたのだろうか?人間の思い込みって、恐ろしい。
しかしながら。
そんなことも含めて、ボブ・ディランは、時代に迎合するのではなくて、時代を自分に迎合させる才能を持っていた。
それでもって。
若いときのディランって、ホントによいのよね、音楽もだけど、ルックスが。伏目がちでナイーブなあの表情、もしも私が当時のアメリカ人女子だったら、絶対にミーハー的なファンになっていたよ!
とはいえ。
ディランの音楽を、現在の私は時おーり好んで聞くが、これはきっと、英語だからいいんだと思う。もしも日本語で同じ内容を歌われたら、鬱陶しくてかなわないような気がする。
しかし、208分は、ちと長いね。
ムスメたちに、「お母さん、また、その映画見てるの?」と、言われ続けた。
「また」じゃなくて、「まだ」だったんだよ。
コメントをみる |